(抜粋)
この5年間、政治は無策だった。無策の犠牲を代表するのが、南相馬市に隣接する浪江町だ。
全町民が避難生活を強いられたこの町では、馬場有町長が代理人となって原発ADR(原子力損害賠償紛争解決センター)に訴えた。しかし東京電力は、この訴えを無視し続けた。その様子を筆者は当サイト(2014年9月11日「始まった『福島一揆』――東日本大震災から3年半」)に詳しく紹介したが、それからさらに、1年半の月日が流れた。申し立てに加わった町民1万5313人のうち440人がその間にこの世を去った。
ここまで来ると、東電のかたくなな姿勢の背後には、おそらくそれを指示しているであろう国の「悪意」が感じ取れる。浪江町民の全員を見殺しにしようという殺意と言っても過言ではない。
「東 北人は負け方を知っている」と、東北地方の民俗学を専門とする赤坂憲雄学習院大学教授は言う。東北の歴史は負け続ける歴史だった。だが、今、浪江町で繰り 広げられているのは、究極の敗北である。そして勝負の勝者が東電以上に国であるところに、この原発事故の歴史的意味がある。
「見せしめ」としてさらし者に
事故から1年後の2012年3月、筆者はやはり当サイトで、福島に関する国の無策を「棄民」と批判した(2012年3月11日「福島が消える――歴史に刻まれる現代の『棄民』」)。それから4年。「無策」は「悪意」に転じた。何が変わったのか。
当初の「無策」の犠牲者は福島県民全員だった。避難した住民全員の「帰還」が政策目標に掲げられたが、それはどちらかといえば具体策のない精神的な努力目標に近いものだった。
しかし、昨年から国の姿勢ははっきり変わった。とりわけ自主避難者には、期限を切って補償を限定する方針に転換したのである。帰還しなければ補償を打ち切る――対象者を絞り込んだ棄民だ。それは、換言すれば棄民の対象の「選別」である。
国の政策を受け入れなければどんな前途がまっているか。国はもはや、国民を棄てて見殺しにすることもいとわない。あからさまな脅しである。浪江の町民は今、その「見せしめ」としてさらし者になっているようにも見える。
(略)
国による選別
今年2月に公開された『大地を受け継ぐ』は一風変わったドキュメンタリー映画だ。主 人公は福島・須賀川市の農民、樽川和也さん。ドキュメンタリーといっても、ほとんどが樽川さんの独白である。この映画の鋭さは、樽川さんの言葉を通して原 発問題のタブーに触れているところだ。
放射能汚染を苦に自殺した父親の後を継いだ樽川さんは、自分の作る農作物を自分では食べられないと告 白する。もちろん出荷する産物は放射線量の基準を厳しく守っているのだが、「それでも食べる気にならない」。放射能をこわがる消費者の気持ちがよく分かる と苦しそうに話す。「これは風評問題ではなく現実なんだ」。
これまで、消費者が放射能をこわがる気持ちを率直に言えば、それは福島の農家へ の差別を助長するとして、逆に非難の的になることもあった。樽川さんの言葉は、父を失った農民だからこそ言えることだ。しかし、だからといって、その点を 曖昧にし続ければ、福島の野菜が安値でしか売れない理由はわからない。結局、曖昧になるのは東電の責任であり、政府の責任であることを映画は訴える。
問題の核心はここにある。責任が曖昧になれば、東電は救われるが、被害者は救われない。国による選別の向かう先は加害者ではなく被害者だけ。国に幻想を持ってはならないと樽川さんは言っているようだ。
(略)
4月に避難指示が解除され、旅館が営業を始めても、ちゃんとした事業だから家賃を払っても成立させる。「そこは主婦の強み。家内工業の形で人件費の安い労働力を確保するから、大丈夫」と、グループの中心となる、同旅館の若女将、小林友子さん(63)は言う。
事業を始める動機は「とにかく何かやらなきゃ」。震災と原発に襲いかかられて、周囲がみんな落ち込んでいるのに、「私たちまで落ち込んでいたら救いがない」。やれば必ずできるという「超楽観主義」だ。
国や市に期待しても何も出て来ないから自分でやる。「女はうだうだ考える前にまず動く。できることからまずやっていくのよ。失敗してももともとじゃない」
他に養蚕を手がけて絹製品を開発する計画もある。「本当の事業として完成するまでに5年か10年かかるかもしれないけど、それまでの時間を笑って過ごそうよ、ということなの」
放射能の線量管理も「自分たちの目で安全を確認する。自分の目で事業が成立することを証明する。それができずにどうするのよ」
今風に言えば、「闘う女集団」の誕生だ。しかし、それを可能にした地域社会の背景を小林さんの口から聞いたとき、筆者は心底感心した。
そ れは、一言で言えば地域社会の権力交替である。震災、原発事故が彼女たちの家庭にもたらした最大の変化は、老人たちが元気を失ったことなのだという。老人 たちはふさぎ込むことが多くなり、目に見えて気力が衰えていった。自分たちが平和に暮らしてきた世界が一変したことに強い衝撃を受けたのだ。
「それはたしかに気の毒なのだけど、私たち嫁の立場の女にとっては、暮らしの中で重しがとれたのよ。私たちは今、自由になったの」
こんなあけすけな表現自体が、彼女たちの今の自由を証明しているともいえよう。震災と原発事故が彼女たちにもたらした初めての自由。
地域共同体の崩壊の否定的な面ばかりに目を奪われてきた筆者に、それは新鮮な驚きだった。
(略)
「女の革命」の行方は……
今、家庭や地域社会の束縛から解き放たれた彼女たちは、底抜けに明るい。明るさは力である。その力は、あるいは原町地区、南相馬市、そして日本という国を変えていくのではないかとさえ思わせる。
「そのうち、男が役に立つ場面もくるでしょ。そうなれば男たちもついてくるわよ」
「原発事故で死んだ人間はいない」とほざいた愚かな与党の女性政調会長や、下着泥棒の”前科”を噂される女性蔑視の代表者のような復興大臣が彼女たちの視線をさらに鋭くする。
地域社会、そして日本の復興を考えるとき、この事実は重要だ。必要なのは行政の計画や政治の段取りなどではない。これまで地域住民や国民を縛ってきた「重し」、国が自ら押しつけてきたしがらみや束縛を取り除けばいいのだ。
Featured Topics / 特集
-
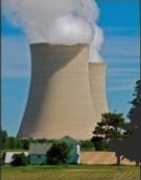
A nuclear power plant in Byron, Illinois. Taken by photographer Joseph Pobereskin (http://pobereskin.com). カレンダー
-
Latest Posts / 最新記事
- President Trump’s radical attack on radiation safety via Bulletin of the Atomic Scientists 2025/10/27
- ‘It’s Sellafield or nothing’: what life is like growing up in the shadow of Europe’s oldest nuclear site via The Guardian 2025/10/07
- Holtec’s announcement that Palisades has transitioned back to “operations status” via Beyond Nuclear 2025/08/27
- Israel attacks Iran: What we know so far via Aljazeera 2025/06/13
- 核ごみ施設受け入れゼロ 全国47知事アンケートvia YAHOO!JAPANニュース (共同) 2025/06/12
Discussion / 最新の議論
- Leonsz on Combating corrosion in the world’s aging nuclear reactors via c&en
- Mark Ultra on Special Report: Help wanted in Fukushima: Low pay, high risks and gangsters via Reuters
- Grom Montenegro on Duke Energy’s shell game via Beyond Nuclear International
- Jim Rice on Trinity: “The most significant hazard of the entire Manhattan Project” via Bulletin of Atomic Scientists
- Barbarra BBonney on COVID-19 spreading among workers on Fukushima plant, related projects via The Mainichi
Archives / 月別アーカイブ
- October 2025 (2)
- August 2025 (1)
- June 2025 (2)
- May 2025 (10)
- February 2025 (1)
- November 2024 (3)
- October 2024 (1)
- September 2024 (5)
- July 2024 (4)
- June 2024 (3)
- March 2024 (1)
- February 2024 (6)
- January 2024 (4)
- November 2023 (8)
- October 2023 (1)
- September 2023 (7)
- August 2023 (5)
- July 2023 (10)
- June 2023 (12)
- May 2023 (15)
- April 2023 (17)
- March 2023 (20)
- February 2023 (19)
- January 2023 (31)
- December 2022 (11)
- November 2022 (12)
- October 2022 (7)
- September 2022 (6)
- August 2022 (22)
- July 2022 (29)
- June 2022 (15)
- May 2022 (46)
- April 2022 (36)
- March 2022 (47)
- February 2022 (24)
- January 2022 (57)
- December 2021 (27)
- November 2021 (32)
- October 2021 (48)
- September 2021 (56)
- August 2021 (53)
- July 2021 (60)
- June 2021 (55)
- May 2021 (48)
- April 2021 (64)
- March 2021 (93)
- February 2021 (69)
- January 2021 (91)
- December 2020 (104)
- November 2020 (126)
- October 2020 (122)
- September 2020 (66)
- August 2020 (63)
- July 2020 (56)
- June 2020 (70)
- May 2020 (54)
- April 2020 (85)
- March 2020 (88)
- February 2020 (97)
- January 2020 (130)
- December 2019 (75)
- November 2019 (106)
- October 2019 (138)
- September 2019 (102)
- August 2019 (99)
- July 2019 (76)
- June 2019 (52)
- May 2019 (92)
- April 2019 (121)
- March 2019 (174)
- February 2019 (146)
- January 2019 (149)
- December 2018 (38)
- November 2018 (51)
- October 2018 (89)
- September 2018 (118)
- August 2018 (194)
- July 2018 (22)
- June 2018 (96)
- May 2018 (240)
- April 2018 (185)
- March 2018 (106)
- February 2018 (165)
- January 2018 (241)
- December 2017 (113)
- November 2017 (198)
- October 2017 (198)
- September 2017 (226)
- August 2017 (219)
- July 2017 (258)
- June 2017 (240)
- May 2017 (195)
- April 2017 (176)
- March 2017 (115)
- February 2017 (195)
- January 2017 (180)
- December 2016 (116)
- November 2016 (115)
- October 2016 (177)
- September 2016 (178)
- August 2016 (158)
- July 2016 (201)
- June 2016 (73)
- May 2016 (195)
- April 2016 (183)
- March 2016 (201)
- February 2016 (154)
- January 2016 (161)
- December 2015 (141)
- November 2015 (153)
- October 2015 (212)
- September 2015 (163)
- August 2015 (189)
- July 2015 (178)
- June 2015 (150)
- May 2015 (175)
- April 2015 (155)
- March 2015 (153)
- February 2015 (132)
- January 2015 (158)
- December 2014 (109)
- November 2014 (192)
- October 2014 (206)
- September 2014 (206)
- August 2014 (208)
- July 2014 (178)
- June 2014 (155)
- May 2014 (209)
- April 2014 (242)
- March 2014 (190)
- February 2014 (170)
- January 2014 (227)
- December 2013 (137)
- November 2013 (164)
- October 2013 (200)
- September 2013 (255)
- August 2013 (198)
- July 2013 (208)
- June 2013 (231)
- May 2013 (174)
- April 2013 (156)
- March 2013 (199)
- February 2013 (191)
- January 2013 (173)
- December 2012 (92)
- November 2012 (198)
- October 2012 (229)
- September 2012 (207)
- August 2012 (255)
- July 2012 (347)
- June 2012 (230)
- May 2012 (168)
- April 2012 (116)
- March 2012 (150)
- February 2012 (198)
- January 2012 (292)
- December 2011 (251)
- November 2011 (252)
- October 2011 (364)
- September 2011 (288)
- August 2011 (513)
- July 2011 (592)
- June 2011 (253)
- May 2011 (251)
- April 2011 (571)
- March 2011 (494)
- February 2011 (1)
- December 2010 (1)
Top Topics / TOPトピック
- anti-nuclear
- Atomic Age
- Capitalism
- East Japan Earthquake + Fukushima
- energy policy
- EU
- France
- Hanford
- health
- Hiroshima/Nagasaki
- Inequality
- labor
- Nuclear power
- nuclear waste
- Nuclear Weapons
- Radiation exposure
- Russia/Ukraine/Chernobyl
- Safety
- TEPCO
- U.S.
- UK
- エネルギー政策
- メディア
- ロシア/ウクライナ/チェルノブイリ
- 健康
- 公正・共生
- 兵器
- 再稼働
- 労働における公正・平等
- 原子力規制委員会
- 原発推進
- 反原発運動
- 大飯原発
- 安全
- 広島・長崎
- 廃炉
- 東京電力
- 東日本大震災・福島原発
- 汚染水
- 米国
- 脱原発
- 被ばく
- 資本主義
- 除染
- 食の安全
Choose Language / 言語



