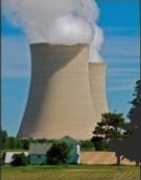添田孝文
[…]
地震と津波だけなら助かった
証人は、福島第一原発から4.5キロの場所にある大熊町の双葉病院で、事故当時、副看護部長を務めていた鴨川一恵さん。同病院で1988年から働いていたベテランだ。避難の途上で亡くなった患者について、検察官役の弁護士が「地震と津波だけなら助かったか」という質問に「そうですね、病院が壊れて大変な状況でも、助けられた」と述べた。
[…]
継続的な点滴やたんの吸引が必要な寝たきり患者が多く、せいぜい1時間程度の移送にしか耐えられないと医師が診断していた人たちだ。本当は、救急車などで寝かせたまま運ぶことが望まれていた。
鴨川さんは、「バスの扉を開けた瞬間に異臭がして衝撃を受けた。座ったまま亡くなっている人もいた」と証言した。バスの中で3人が亡くなっていたが「今、息を引き取ったという顔ではなかった」。体育館に運ばれたあとも、11人が亡くなった。
高い線量、連絡や避難困難に
福島第一3号機が爆発した3月14日に、双葉病院で患者の搬送にあたっていた自衛官の調書も読み上げられた。「どんと突き上げる爆発、原発から白煙が上がっていた」「バスが一台も戻ってくる気配がないので、衛星電話を使わせてもらおうと、(双葉病院から約700m離れた)オフサイトセンターに向かいました。被曝するからと、オフサイトセンターに入れてもらうことが出来ませんでした」。
オフサイトセンター付近の放射線量は、高い時は1時間あたり1mSv、建物の中でも0.1mSvを超える状態で、放射性物質が建物に入るのを防ぐために、出入り口や窓がテープで目張りされていた。自衛官はオフサイトセンターに入ることが出来なかったため、持っていたノートをちぎって「患者90人、職員6人取り残されている」と書き、玄関ドアのガラスに貼り付けた。
病院からの患者の搬送作業の最中、線量計は鳴りっぱなしですぐに積算3mSvに達し、「もうだめだ、逃げろ」と自衛隊の活動が中断された様子や、県職員らが「このままでは死んじゃう」と県内の医療機関に電話をかけ続けても受け入れ先が確保できず、バスが県庁前で立ち往生した状況についても、供述が紹介された。
これまで、政府事故調の報告書などで、おおまかな事実関係は明らかにされていた。しかし、当事者たちの証言や供述で明らかになった詳細な内容は、驚きの連続だった。刑事裁判に役立つだけでなく、今後の原子力災害対応の教訓として、貴重な情報が多く含まれていたように思えた。