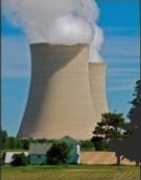[…]
稼働していた原子炉4基は揺れを感知して自動停止。7基すべてが翌朝までに冷温停止となり、「安全機能は問題なく確保された」(同副所長)ためだ。施設のダメージの大きさに驚きながらも、肝心のところは大丈夫だったのだと妙に納得したことを覚えている。
その5年前の02年、東電では同原発や福島第1、第2原発でトラブル記録を改ざん・隠蔽していたことが発覚。歴代社長4人が引責辞任する「トラブル隠し事件」が起きている。明らかに不正な行為があったのだが、このときも国民の原発の安全性への不安が高まることはなかった。「日本の技術は優れている」という考えが強かったためだ。
[…]
11年3月11日、福島第1原発に致命傷を与えたのは、地震発生の約50分後に押し寄せた約15メートルの津波だった。非常用電源が水没し、原子炉を冷やす機能を喪失。1~3号機のメルトダウン、建屋の水素爆発と、坂を転げ落ちるように事態はエスカレートしていった。
同事故の責任や教訓を考えるとき、2つの視点がある。1つは巨大津波への備えがあったかどうか。06年に当時の原子力安全委員会が、津波対策を盛り込んだ耐震設計審査指針をまとめていたものの福島第1など既存原発へのチェック作業が遅れていたことが分かっている。これはその後の裁判の争点にもなっている。
もう1つの視点は、事故の発生後、その進展を食い止める適切な対応が取られたかという問題だ。
[…]
だが、原発の安全問題に詳しい田辺文也・社会技術システム安全研究所所長によると、東電の現場はこの徴候ベース手順を参照した形跡がないという。「手順に従っていれば、少なくとも2号機と3号機ではメルトダウンを回避することは十分可能だった」と分析している。
99年9月、国内で初めて事故被曝(ひばく)による犠牲者を出したジェー・シー・オー(JCO)臨界事故や、廃炉が決まった高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の一連のトラブルも、日本の原子力技術を使いこなす能力に疑問を抱かせるものだった。
JCO事故は、ウラン燃料を混合する作業で、作業効率を優先するあまり臨界の危険の大きい形状の容器を勝手な判断で使っていた。「定められた手順の意味を理解せずに作業をした」(田辺氏)。
もんじゅでは、95年のナトリウム漏れ事故以来、事業者の隠蔽体質が問題になった。「3.11」後はプラントの点検漏れや規制当局への虚偽報告が発覚。高速増殖炉という経験の浅い技術に向き合う上での謙虚さを欠いた姿勢があらわになった。
原子力の事業者や規制機関は、リスクを抱えた巨大システムを扱う自覚と能力を欠いたまま走ってきた印象がぬぐえない。日本の原子力事故は「想定外」の事態への対策を講じたつもりが、別の予想外の事態に直面するという繰り返しだった。原子力安全を巡る課題はポスト平成に持ち越された。(吉川和輝)
■証言 黒川清 政策研究大学院大客員教授が語る
福島第1原子力発電所の事故の原因を究明するため、2011年12月に国会に調査委員会(国会事故調)が設置され、委員長として翌7月に報告書を提出した。
報告書の結論は、この事故が地震や津波による自然災害ではなく「規制の虜(とりこ)」に陥ったための人災であったということだ。規制する側の政府が、東京電力など規制される側に取り込まれた構造になっていて規制が手抜きになっていた。日本の原発では過酷事故は起こらないという虚構がまかり通っていた。政産官学やメディアなど関係者みんなが問題を知りながら対応してこなかった。
こうした日本の組織におけるガバナンスの欠如が福島事故によって世界にさらされたが、何も原発事故に限った話ではない。最近でも次々おこる大企業、官僚などの情けない不祥事も同じ背景だ。
[…]