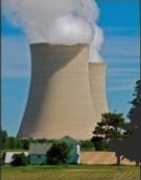■野中留吉さん(1928年生まれ)
13人。野中留吉(のなかとめよし)さん(89)が原爆で失った親族の数だ。当時17歳。父が他界し、長崎市の旧江平町に母や妹と住んでいた。近くには長姉とその家族が居を構えた。子どもは5人。被爆したその年に生まれたばかりの子もいた。
(略)
被爆翌日の朝。野中さんは、まだ夜が明けないうちに再び我が家へ向かった。母は、妹は無事か。たどり着くと、がれきと白い煙の中、必死にその姿を捜した。
見つけたのは、腕や足、顔が白骨となり、それ以外は黒い炭となった遺体だった。確かめるすべはなかったが、「母だ」と直感した。少なくとも、そう信じようとした。
白骨と化したその顔は、大きく口を開けていた。母は炎の中で何を叫んだのだろうか。野中さんは今でも考えることがあるという。「助けて」あるいは、息子の身を案じて、「留吉」と呼び続けたのかもしれない。
(略)
被爆数日後から救援食が配られ始め、野中さんはそれを姉一家4人に食べさせた。
しかし5歳ほどの三男・道秀さんは食べ物を受け付けなくなった。長女と次男は口にしたが、3人とも口の周りに水ぶくれができ始めた。6日目、道秀さんが亡くなった。
道秀さんを火葬した日の夜、野中さんは姉・エキさんから病床に呼ばれた。「うちも朝までもつかわからんとよ。子ども2人を頼むけんね」。野中さんは「冗談じゃなか。姉ちゃんがお袋代わりになってもらわないかん」と返した。まだ17歳。家族が恋しかった。
夜更けになり、「留吉」と呼ぶ声が聞こえた。母方の叔父たちが、出津から救援に来てくれたのだ。姉一家の状況を見た叔父たちは「何とかして早う運ばんと」。ゆりかごで3人を運び、出津から乗ってきた舟に乗せた。
翌朝、エキさんは舟の上で「故郷の水を飲んで死にたかった」と言い残して亡くなった。母の遺体を前にした時は出なかった涙が、その時は止まらなかった。
その直後、おいの忠義さんに聞かれた。「お母ちゃんは?」
野中さんは「そこに寝とるたい。じっと寝とかんね」と制したが、忠義さんは「お母ちゃんの所に行くけん」とせがんだ。手を組ませてほしいと言われてその通りにすると、目を閉じて息を引き取った。母、そして自らの死期を感じ取ったのだろうか。
(略)
戦後間もないころ、会社の労働組合で、ある問題が起きた。「職場の規律を乱した」として、青年部の会員を解雇するという提案が会社の懲戒委員会からあった。その工員は今でいうタイムカードを後輩に代行させ、自分は働かずに街へ出て遊んでいたという。
ただ当時は、職場の規律自体が確立されていなかった。野中さんは、会社としてそういう態勢をとらないまま社員を罰するのはおかしいのではないかと思った。職場大会で「首を切るのは反対」と発言すると、それを聞いた青年部長が「あいつを役員に使え」。地区の役員を任されることになり、そこから組合の経験が始まった。50歳ごろまで、「組合の仕事にまみれてきた」と振り返る。
1956年、第2回原水爆禁止世界大会が長崎で開かれた。野中さんが役員をしていた青年部は、大会の準備・設営にかり出されることになった。設営に汗を流しながら、「世界大会が成功するように」と強く願ったことを覚えている。
今年89歳を迎えた野中さん。原爆に遭った同僚や仲間はほとんどが亡くなった。
原爆で13人もの親族を失った経験を、あまり積極的には語ってこなかった。同じく長崎で被爆した妻のフクヨさん(86)とも「涙流して深刻に語り合うなんてことはなかね」。
取材中、何度も「僕の話は記事にならない」と言われた。「原爆の孤児になりながら、原爆に対する憎しみをどう僕は持っているのか。それがどういう形で僕の生活に反映されているか。でもそれはなかとよ、率直な話。非常に期待を裏切ることになるけど」
ビキニ水爆、第五福竜丸、チェルノブイリ……。ことあるごとに核反対の声は大きくなった。しかし、「ソ連の原爆は人民の平和のための武器。米国の原爆は侵略の道具」と言う人もおり、違和感を覚えることもあった。
声高には叫ばないが、心では平和を願い続ける。平和祈念式典には欠かさず足を運ぶ。「争いが地球からなくなってほしい」。午前11時2分の鐘を聞きながら、いつも思うことだ。
関連記事: