(略)
「親から小遣いなんてもらったこともない。新聞配達で稼ぐ、そんな子供ばかりだった」。町内の自営業の男性(72)は、原発建設以前の昭和30年代をこう振り返る。
父は漁師だった。だが船が小さく、満足な漁獲も得られない。土木作業で日銭を得る毎日だった。
懐中時計を質店に持ち込み、金を受け取る。そんなおつかいを頼まれたこともあった。「貧しかったのは私だけでない。町のあちこちが苦しかった」
町は小さな農村や漁村ばかりで、主だった産業はない。企業誘致もままならず、働き口を求めて若者は都市部に流出した。
そこで起死回生の策が持ち上がった。原発の誘致だった。
高浜原発1号機は49年に運転開始。50年に2号機が稼働し、60年には3、4号機が続いた。
「関電の仕事の方が給料が高くて、地元住民はみんなそちらで働いた。人手が足りないと地元業者に泣きつかれたこともあった」。57年から平成8年まで町長を務めた田中通(とおる)氏(93)が語る。
県道の整備、貿易港の開港…。原発建設を機に町は一変した。数々の恩恵を町誌はこう刻む。《財政規模は増大し、町は飛躍的に発展した》
* * *
地元で高浜原発誘致の立役者とされる元助役の森山栄治氏(故人)は関電にとっても「功労者」だった。
「先生のおかげでこのように立派になることができました」
関電の原子力事業本部(同県美浜町)の幹部の1人は、異動で本部を離れるにあたり森山氏の元にあいさつに出向いた。高浜原発の地元対策を図る上で重要な人物だったからだ。
それゆえ、関電は原子力事業本部に森山氏との窓口となる担当者を置いた。
森山氏は担当者からの連絡がしばらく途絶えたり、休日に電話してつながらなかったりすると激怒した。それでも関電は、森山氏との良好な関係が欠かせないと考えていた。幹部であっても担当者はへりくだるように接するしかなかった。
原子力事業を円滑に進めるため-。町の「大物」はこうして作られていった。
原発の建設や運転、再稼働には地元合意が不可欠だ。一方、原発が立地する自治体には国の交付金や電力会社からの税収などのメリットがあり、持ちつ持たれつの関係を築いている。人口約1万人の高浜町では、100億円ほどの一般会計のうち原子力関連収入が50%を占める。
(略)
* * *
今回の不祥事を受けても、関電が原発事業を進める上で地元への配慮は無くすことはない。廃炉が決定している美浜原発1、2号機(美浜町)についても、地元で相談会などを開いて関連工事などの発注を増やす方針だ。
Featured Topics / 特集
-
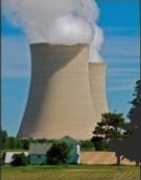
A nuclear power plant in Byron, Illinois. Taken by photographer Joseph Pobereskin (http://pobereskin.com). カレンダー
-
Latest Posts / 最新記事
- Israel attacks Iran: What we know so far via Aljazeera 2025/06/13
- 核ごみ施設受け入れゼロ 全国47知事アンケートvia YAHOO!JAPANニュース (共同) 2025/06/12
- Trump Administration Gutting Regulatory Agency, Recent Nuclear Incidents, Coverup: No Time to Open Illinois for More Nuclear Power, Nuclear Watchdog Group Asserts via Nuclear Energy Information Service Illinois 2025/05/28
- Fukushima soil headed to Japan PM’s flower beds to allay nuclear safety fears via The Guardian 2025/05/28
- US East Coast faces rising seas as crucial Atlantic current slows via New Scientist 2025/05/26
Discussion / 最新の議論
- Leonsz on Combating corrosion in the world’s aging nuclear reactors via c&en
- Mark Ultra on Special Report: Help wanted in Fukushima: Low pay, high risks and gangsters via Reuters
- Grom Montenegro on Duke Energy’s shell game via Beyond Nuclear International
- Jim Rice on Trinity: “The most significant hazard of the entire Manhattan Project” via Bulletin of Atomic Scientists
- Barbarra BBonney on COVID-19 spreading among workers on Fukushima plant, related projects via The Mainichi
Archives / 月別アーカイブ
- June 2025 (2)
- May 2025 (10)
- February 2025 (1)
- November 2024 (3)
- October 2024 (1)
- September 2024 (5)
- July 2024 (4)
- June 2024 (3)
- March 2024 (1)
- February 2024 (6)
- January 2024 (4)
- November 2023 (8)
- October 2023 (1)
- September 2023 (7)
- August 2023 (5)
- July 2023 (10)
- June 2023 (12)
- May 2023 (15)
- April 2023 (17)
- March 2023 (20)
- February 2023 (19)
- January 2023 (31)
- December 2022 (11)
- November 2022 (12)
- October 2022 (7)
- September 2022 (6)
- August 2022 (22)
- July 2022 (29)
- June 2022 (15)
- May 2022 (46)
- April 2022 (36)
- March 2022 (47)
- February 2022 (24)
- January 2022 (57)
- December 2021 (27)
- November 2021 (32)
- October 2021 (48)
- September 2021 (56)
- August 2021 (53)
- July 2021 (60)
- June 2021 (55)
- May 2021 (48)
- April 2021 (64)
- March 2021 (93)
- February 2021 (69)
- January 2021 (91)
- December 2020 (104)
- November 2020 (126)
- October 2020 (122)
- September 2020 (66)
- August 2020 (63)
- July 2020 (56)
- June 2020 (70)
- May 2020 (54)
- April 2020 (85)
- March 2020 (88)
- February 2020 (97)
- January 2020 (130)
- December 2019 (75)
- November 2019 (106)
- October 2019 (138)
- September 2019 (102)
- August 2019 (99)
- July 2019 (76)
- June 2019 (52)
- May 2019 (92)
- April 2019 (121)
- March 2019 (174)
- February 2019 (146)
- January 2019 (149)
- December 2018 (38)
- November 2018 (51)
- October 2018 (89)
- September 2018 (118)
- August 2018 (194)
- July 2018 (22)
- June 2018 (96)
- May 2018 (240)
- April 2018 (185)
- March 2018 (106)
- February 2018 (165)
- January 2018 (241)
- December 2017 (113)
- November 2017 (198)
- October 2017 (198)
- September 2017 (226)
- August 2017 (219)
- July 2017 (258)
- June 2017 (240)
- May 2017 (195)
- April 2017 (176)
- March 2017 (115)
- February 2017 (195)
- January 2017 (180)
- December 2016 (116)
- November 2016 (115)
- October 2016 (177)
- September 2016 (178)
- August 2016 (158)
- July 2016 (201)
- June 2016 (73)
- May 2016 (195)
- April 2016 (183)
- March 2016 (201)
- February 2016 (154)
- January 2016 (161)
- December 2015 (141)
- November 2015 (153)
- October 2015 (212)
- September 2015 (163)
- August 2015 (189)
- July 2015 (178)
- June 2015 (150)
- May 2015 (175)
- April 2015 (155)
- March 2015 (153)
- February 2015 (132)
- January 2015 (158)
- December 2014 (109)
- November 2014 (192)
- October 2014 (206)
- September 2014 (206)
- August 2014 (208)
- July 2014 (178)
- June 2014 (155)
- May 2014 (209)
- April 2014 (242)
- March 2014 (190)
- February 2014 (170)
- January 2014 (227)
- December 2013 (137)
- November 2013 (164)
- October 2013 (200)
- September 2013 (255)
- August 2013 (198)
- July 2013 (208)
- June 2013 (231)
- May 2013 (174)
- April 2013 (156)
- March 2013 (199)
- February 2013 (191)
- January 2013 (173)
- December 2012 (92)
- November 2012 (198)
- October 2012 (229)
- September 2012 (207)
- August 2012 (255)
- July 2012 (347)
- June 2012 (230)
- May 2012 (168)
- April 2012 (116)
- March 2012 (150)
- February 2012 (198)
- January 2012 (292)
- December 2011 (251)
- November 2011 (252)
- October 2011 (364)
- September 2011 (288)
- August 2011 (513)
- July 2011 (592)
- June 2011 (253)
- May 2011 (251)
- April 2011 (571)
- March 2011 (494)
- February 2011 (1)
- December 2010 (1)
Top Topics / TOPトピック
- anti-nuclear
- Atomic Age
- Capitalism
- East Japan Earthquake + Fukushima
- energy policy
- EU
- France
- Hanford
- health
- Hiroshima/Nagasaki
- Inequality
- labor
- Nuclear power
- nuclear waste
- Nuclear Weapons
- Radiation exposure
- Russia/Ukraine/Chernobyl
- Safety
- TEPCO
- U.S.
- UK
- エネルギー政策
- メディア
- ロシア/ウクライナ/チェルノブイリ
- 健康
- 公正・共生
- 兵器
- 再稼働
- 労働における公正・平等
- 原子力規制委員会
- 原発推進
- 反原発運動
- 大飯原発
- 安全
- 広島・長崎
- 廃炉
- 東京電力
- 東日本大震災・福島原発
- 汚染水
- 米国
- 脱原発
- 被ばく
- 資本主義
- 除染
- 食の安全
Choose Language / 言語



