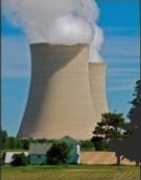この本を読み進めるうち、私は大きな衝撃を受けざるを得なかった。それは証言者の中で、「土方」仕事を経験しており、山谷や釜ヶ崎のようなドヤ街から流れてきた労動者が少なくなかったことだ。
山谷、土方、日雇い、ドヤ街、そして原発。
そこに生きる人びとの人生、彼らが抱える問題に対して、すでに無関心ではいられなくなっている自分がいた。
マスクなんかしていられない
「宿泊先は山谷のつばめ荘だった。そこから毎日、工務店に通っただ。せんべい布団一枚で一泊七十円。仕送りするには、こんな所に泊まるしかなかったわけよ」
『闇に消される原発被曝者』には、福島県双葉町出身の大久保智光さんのこんな証言が書かれている。
大久保さんは終戦を海南島で迎え、戦後は、闇屋や長野のダム建設にたずさわり、食いっぱぐれのない農業をやっていく決意をする。しかしそれだけでは一家を養えない。山谷に出てきて日雇い仕事をしていた大久保さんだったが、やがて福島第一原発で働き始める。出稼ぎが普通であった農家にとって、1971(昭和46)年に稼働しはじめた原発は、地元で現金収入を得られる格好の働き口となった。
しかし、原発内での労働は過酷なものだった。大久保さんは「暑くて、苦しくてたまらなくなって、防毒マスクをはずして仕事をしたもんだ。今思うと余計に放射能をいっぱい吸い込んでいたんだ!」と証言している。マスクというのはもちろん放射能による内部被曝を防ぐためのものだ。しかし実際は暑くて現場で使えない。
これは大久保さん一人が体験したことではない。労働者として原発に入り込み、原発内部の実態を描いた堀江邦夫『原発ジプシー』でも、次のように書かれている。
原子炉建屋にくらべ、タービン建屋内はさほど(放射)線量は高くない。アラーム・メーターも鳴らない。それだけに作業時間は長くなる。その間、反面マスクをつけたままだ。息苦しい。頭痛もしてくる。
最初のころは、真面目にマスクをつけていた。だが、ほとんどの労動者はマスクを首にぶら下げているだけだ。私もついつい彼らの仲間入りをすることが多くなってしまった。「内部被ばく」への不安よりも、その場の肉体的苦痛から逃れたい気持の方が強いのだ。そこで働く労動者がどれだけ過酷な状況で使うかが全く考慮されていないこのマスクについては他にも、作業の説明をその場で仲間にする時に声が聞こえないので結局外して作業する、といったことが起きている。
もっと読む。