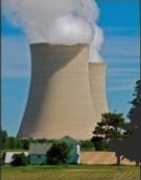広島と長崎に設置されていた米原爆傷害調査委員会(ABCC)の医師が1950年代半ば、米政府の公式見解に異を唱え、原爆投下直後に降った「黒い雨」が住民たちの病気の原因になった可能性があると指摘していた。しかし、被爆75年を迎える今も、黒い雨の健康への影響を巡って論争が続く。なぜ、医師の訴えは届かず、黒い雨による「被ばく」は置き去りにされたのか。【小山美砂】
目に見えない問題に時間割けず
「広島の残留放射線及び放射線による兆候と症状」と題した9ページの報告書。添付された広島市の地図には、48個の小さな丸印が書かれている。原爆の爆心地からの距離は2~6・5キロ。いずれも爆発時に放出された直接放射線の影響がほとんどないとされた場所だ。だが、そこにいた人たちも脱毛や紫斑などの急性症状に見舞われた。「現在入手できる客観的証拠では、原爆投下後の残留放射線は無視できるとされている。なのに放射線を浴びた時の兆候や症状が表れている」。報告書は矛盾を指摘する。
報告書を作ったのはABCCの生物統計部長、ローウェル・ウッドベリー医師(故人)。原爆放射線による人体への影響を調査する研究の中枢にいた。
広島では原爆投下直後、原子雲や火災に伴ってできた積乱雲から、核分裂で飛び散った放射性物質を含む黒い雨が降った。爆風で巻き上げられたほこりやちりも放射性物質とともに広範囲に落ちた。多くの人が浴び、空気や水、食物と一緒に体内に取り込んで被ばくしたと考えられる。
だが、米政府は一貫して直接放射線以外の放射線の影響を否定した。被爆1カ月後の45年9月12日、広島・長崎を視察した原爆製造計画「マンハッタン計画」の副責任者だった米軍准将が「広島の廃虚に残留する放射線はない」と発表し、翌日の米紙ニューヨーク・タイムズが報じた。
「。。。」
放射性降下物が病気を招いたと考えるウッドベリー氏が、米本国のスタッフォード・ウォーレン医師(故人)らに異論を伝えたのはこの頃だ。だが、壁は厚かった。ウォーレン氏はマンハッタン計画の安全対策責任者。放射能を洗い流したといわれる45年9月中旬の枕崎台風の前後に広島と長崎に入り「患者の障害は危険な量の放射能が地上に残った結果ではない」と報告して政府見解を支えた。核開発にその後も関わった放射線研究の権威にウッドベリー氏ははね返され、政府を動かすことはできなかった。
ABCC内部で黒い雨はどう見られていたのか。「組織として『調査をしよう』という動きはなかった」。当時、ABCCの印刷課にいた宮川寅二さん(93)=広島市南区=は証言する。ABCCは広島と長崎の被爆者ら約12万人を対象に55年ごろに始めた寿命調査で「黒い雨に遭ったか」との質問を設けた。質問票の書式を任された宮川さんは「余白ができたから盛り込んだだけだった」と言う。
宮川さんの質問票が使われた61年までの調査に対し、約1万3000人が黒い雨に遭ったと回答した。しかし、75年にABCCが日米共同運営の放射線影響研究所(放影研)に改組された後も、長崎の医師らが回答の存在を2011年に指摘するまで「黒い雨に遭った場所や時間の情報が不十分だった」との理由で解析しなかった。
[…]
疑われるなら国は救済を
国による被爆者援護は、原爆投下から12年後の1957年に原爆医療法(現被爆者援護法)が施行されて始まった。対象地域の拡大や手当の創設などが進められ、黒い雨を巡っては76年、広島の爆心地から北西側に広がる長さ約19キロ、幅約11キロの楕円(だえん)状の地域が援護対象区域に指定された。この区域にいた人は無料で健康診断を受けられ、国が「放射線の影響を否定できない」と定める11障害を伴う病気になれば、医療費が免除になる被爆者健康手帳を受け取れる。
しかし、国は80年に厚相(当時)の諮問機関が出した「被爆地域の指定は科学的・合理的根拠のある場合に限定して行うべきだ」との意見書を盾に、区域の見直しをしなかった。黒い雨に遭った人の高齢化も進み、広島市や県は2008年、3万人超を対象にアンケートを実施。援護区域の6倍の広さで黒い雨が降ったとして国に区域拡大を求めたが「60年前の記憶によっていて、正確性が明らかにできない」と退けられた。
黒い雨の健康被害を認めない国がよりどころにするのが、45年8~11月の現地調査などのデータから放影研が作り、被ばく推定線量の計算に使われる評価システムだ。放影研は87年に出したシステムに関する報告書で「残留放射線の影響は無視できる程度に少ない」との見解を示している。
「直接放射線による外部被ばくだけでは、被爆者にもたらされた健康被害の説明がつかない」。19年10月、広島地裁。援護区域外で黒い雨に遭った住民ら84人が被爆者健康手帳の交付を求めた「黒い雨訴訟」で、住民側の証人として出廷した広島大の大瀧慈(めぐ)名誉教授(69)は訴えた。
75年から広島大原爆放射線医科学研究所に勤め、統計学の観点から原爆の影響を見続けてきた。広島市などのアンケートにも携わった研究者に気付きをもたらしたのは、11年3月の東京電力福島第1原発事故だった。
低線量被ばくや内部被ばくが議論される中、広島大が約1万8000人の被爆者を対象に10年までの40年間に実施した健康調査のデータを改めて分析し、黒い雨が降った爆心地の西側では被爆した場所が遠いほど、がんで死亡する割合が高いとの結果が出た。原爆の放射線による健康被害のリスクは爆心地に近いほど高いという「定説」と矛盾する。「放射性物質を空気や水、野菜とともに体内に取り込んだことによる内部被ばくの影響が否定できない」と結論づけた。
放射性物質が体内に入ると、排出されない限り局所的な被ばくが続く。だが、放射線量の測定方法は確立されておらず、がんの発生など健康への影響も解明されていない。被爆者援護法は「他の戦争被害とは異なる特殊の被害」を受けた人々を救済するために制定された。その趣旨を踏まえ、大瀧名誉教授は主張する。「黒い雨の影響で健康被害が生じたと断定できなくても、疑われるなら国は救済すべきだ」。29日に言い渡される判決が、国が内部被ばくと向き合う契機となることを期待している。
全文