(抜粋)
晴れ間が広がった2月上旬の月曜日。日本記者クラブの取材団に参加し、東電福島第一原発の構内に入った。いくつものチェックゲートを通過すると、1~4号機の原子炉建屋を一望できる高台にバスで案内された。
「建物の中には放射性物質が充満しています」
東電担当者が指さした先には、水素爆発で原子炉建屋上部が吹き飛んだ1号機が間近に見えた。1号機の原子炉建屋の最上階では鉄骨があめ細工のように折れ曲がり、事故当時の無残な姿をさらしていた。目線を南側にある3号機に移すと、分厚いコンクリートの壁がぼろぼろに崩れ、鉄筋がむき出しになった原子炉建屋が見えた。
その間にある2号機の原子炉建屋。炉心溶融は起こしたが、爆発をまぬがれ、事故前の姿をかろうじてとどめていた。
この2号機での廃炉に向けた作業が最近注目を浴びた。1月末、遠隔操作によるカメラで調査したところ、2号機の原子炉圧力容器の下にある足場で、溶けた核燃料(デブリ)のような黒い塊が確認されたからだ。
溶けた燃料は、周辺機器のさまざまな金属などと混じりながら、圧力容器の下に流れ落ち、格納容器の底に落ちていると見られる。専門家によっては、飛び散って周辺にこびりついているのかもしれないという見方もある。
(略)
●100年単位の核管理
福島第一原発でチェルノブイリのような石棺は考えられていない。ただ、専門家の間には「選択肢としてあり得る」といった見方は少なくない。吉岡斉・九州大学教授(科学技術史)は「福島第一原発も当面石棺化するしかない。発熱量がわずかなので、何らかの事故があっても核物質の再燃はまず起こらない。100~200年経過すれば、放射線量は相当減るので、その時点で高濃度の物質の取り出しを考えればいい」と指摘する。
原発の推進、反対の立場を問わず聞こえてくるのは、「デブリは確認できても取り出すのは難しいのではないか」との見方だ。東電は廃炉期間を30~40年とするスケジュールを掲げるが、さらに長期化する恐れは十分ある。長期管理も含めた石棺の可能性を否定するだけでは、ふたたび疑念が生じる。正面からとらえて、議論をすべき時期を迎えている。
福島第一原発の敷地内はもはやタンクだらけで、何か別の化学工場の中にいるような気分になる。それというのも、日々、タンクに入れる汚染水の発生が絶えないためだ。
第一原発では、事故直後から、溶けた燃料を冷やすため、1~3号機の建屋に水を注入し続けている。注入された水は溶けた燃料にふれて汚染されるが、地下水なども流入してくるので、入れた量よりも多くの汚染水が出てくる。
海洋放出の現実味
流入する地下水を抑制するために、1~4号機の建屋を氷の壁で覆う凍土壁の設置、建屋地下から水をくみ上げるなどの対策を進めているが、いまだに汚染水が増え続ける。すでに約96万トンの汚染水タンクが敷地内にたまり、その数は1千基に。3階建て相当のタンクが数日でいっぱいになる勢いだ。
(略)
今後の方針を決める別の部会のメンバーでもある東京大学の関谷直也特任准教授(災害社会学)は、「経産省の報告では、漁業が受ける経済被害をコストに含めていない。地元の漁業が再生の途上にあり、放射性物質の国民の理解が十分に進んでいないなかでの放出は時期尚早だ」と国の姿勢の不足を指摘する。
原子力規制委員会も、海洋放出が現実的な対応だとしているが、強く主導するわけでもない。
Featured Topics / 特集
-
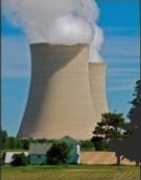
A nuclear power plant in Byron, Illinois. Taken by photographer Joseph Pobereskin (http://pobereskin.com). カレンダー
-
Latest Posts / 最新記事
- Israel attacks Iran: What we know so far via Aljazeera 2025/06/13
- 核ごみ施設受け入れゼロ 全国47知事アンケートvia YAHOO!JAPANニュース (共同) 2025/06/12
- Trump Administration Gutting Regulatory Agency, Recent Nuclear Incidents, Coverup: No Time to Open Illinois for More Nuclear Power, Nuclear Watchdog Group Asserts via Nuclear Energy Information Service Illinois 2025/05/28
- Fukushima soil headed to Japan PM’s flower beds to allay nuclear safety fears via The Guardian 2025/05/28
- US East Coast faces rising seas as crucial Atlantic current slows via New Scientist 2025/05/26
Discussion / 最新の議論
- Leonsz on Combating corrosion in the world’s aging nuclear reactors via c&en
- Mark Ultra on Special Report: Help wanted in Fukushima: Low pay, high risks and gangsters via Reuters
- Grom Montenegro on Duke Energy’s shell game via Beyond Nuclear International
- Jim Rice on Trinity: “The most significant hazard of the entire Manhattan Project” via Bulletin of Atomic Scientists
- Barbarra BBonney on COVID-19 spreading among workers on Fukushima plant, related projects via The Mainichi
Archives / 月別アーカイブ
- June 2025 (2)
- May 2025 (10)
- February 2025 (1)
- November 2024 (3)
- October 2024 (1)
- September 2024 (5)
- July 2024 (4)
- June 2024 (3)
- March 2024 (1)
- February 2024 (6)
- January 2024 (4)
- November 2023 (8)
- October 2023 (1)
- September 2023 (7)
- August 2023 (5)
- July 2023 (10)
- June 2023 (12)
- May 2023 (15)
- April 2023 (17)
- March 2023 (20)
- February 2023 (19)
- January 2023 (31)
- December 2022 (11)
- November 2022 (12)
- October 2022 (7)
- September 2022 (6)
- August 2022 (22)
- July 2022 (29)
- June 2022 (15)
- May 2022 (46)
- April 2022 (36)
- March 2022 (47)
- February 2022 (24)
- January 2022 (57)
- December 2021 (27)
- November 2021 (32)
- October 2021 (48)
- September 2021 (56)
- August 2021 (53)
- July 2021 (60)
- June 2021 (55)
- May 2021 (48)
- April 2021 (64)
- March 2021 (93)
- February 2021 (69)
- January 2021 (91)
- December 2020 (104)
- November 2020 (126)
- October 2020 (122)
- September 2020 (66)
- August 2020 (63)
- July 2020 (56)
- June 2020 (70)
- May 2020 (54)
- April 2020 (85)
- March 2020 (88)
- February 2020 (97)
- January 2020 (130)
- December 2019 (75)
- November 2019 (106)
- October 2019 (138)
- September 2019 (102)
- August 2019 (99)
- July 2019 (76)
- June 2019 (52)
- May 2019 (92)
- April 2019 (121)
- March 2019 (174)
- February 2019 (146)
- January 2019 (149)
- December 2018 (38)
- November 2018 (51)
- October 2018 (89)
- September 2018 (118)
- August 2018 (194)
- July 2018 (22)
- June 2018 (96)
- May 2018 (240)
- April 2018 (185)
- March 2018 (106)
- February 2018 (165)
- January 2018 (241)
- December 2017 (113)
- November 2017 (198)
- October 2017 (198)
- September 2017 (226)
- August 2017 (219)
- July 2017 (258)
- June 2017 (240)
- May 2017 (195)
- April 2017 (176)
- March 2017 (115)
- February 2017 (195)
- January 2017 (180)
- December 2016 (116)
- November 2016 (115)
- October 2016 (177)
- September 2016 (178)
- August 2016 (158)
- July 2016 (201)
- June 2016 (73)
- May 2016 (195)
- April 2016 (183)
- March 2016 (201)
- February 2016 (154)
- January 2016 (161)
- December 2015 (141)
- November 2015 (153)
- October 2015 (212)
- September 2015 (163)
- August 2015 (189)
- July 2015 (178)
- June 2015 (150)
- May 2015 (175)
- April 2015 (155)
- March 2015 (153)
- February 2015 (132)
- January 2015 (158)
- December 2014 (109)
- November 2014 (192)
- October 2014 (206)
- September 2014 (206)
- August 2014 (208)
- July 2014 (178)
- June 2014 (155)
- May 2014 (209)
- April 2014 (242)
- March 2014 (190)
- February 2014 (170)
- January 2014 (227)
- December 2013 (137)
- November 2013 (164)
- October 2013 (200)
- September 2013 (255)
- August 2013 (198)
- July 2013 (208)
- June 2013 (231)
- May 2013 (174)
- April 2013 (156)
- March 2013 (199)
- February 2013 (191)
- January 2013 (173)
- December 2012 (92)
- November 2012 (198)
- October 2012 (229)
- September 2012 (207)
- August 2012 (255)
- July 2012 (347)
- June 2012 (230)
- May 2012 (168)
- April 2012 (116)
- March 2012 (150)
- February 2012 (198)
- January 2012 (292)
- December 2011 (251)
- November 2011 (252)
- October 2011 (364)
- September 2011 (288)
- August 2011 (513)
- July 2011 (592)
- June 2011 (253)
- May 2011 (251)
- April 2011 (571)
- March 2011 (494)
- February 2011 (1)
- December 2010 (1)
Top Topics / TOPトピック
- anti-nuclear
- Atomic Age
- Capitalism
- East Japan Earthquake + Fukushima
- energy policy
- EU
- France
- Hanford
- health
- Hiroshima/Nagasaki
- Inequality
- labor
- Nuclear power
- nuclear waste
- Nuclear Weapons
- Radiation exposure
- Russia/Ukraine/Chernobyl
- Safety
- TEPCO
- U.S.
- UK
- エネルギー政策
- メディア
- ロシア/ウクライナ/チェルノブイリ
- 健康
- 公正・共生
- 兵器
- 再稼働
- 労働における公正・平等
- 原子力規制委員会
- 原発推進
- 反原発運動
- 大飯原発
- 安全
- 広島・長崎
- 廃炉
- 東京電力
- 東日本大震災・福島原発
- 汚染水
- 米国
- 脱原発
- 被ばく
- 資本主義
- 除染
- 食の安全
Choose Language / 言語



