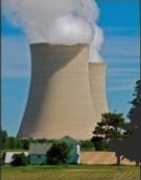「放射線防護は状況に応じた管理目標を幅を持って示し、安全と危険の間に線を引かない考え方を取る。明確な安全基準を求める社会との溝が埋まらなかった」。国際放射線防護委員会(ICRP)委員の甲斐倫明(65)=大分県立看護科学大教授=は、東京電力福島第1原発事故後の放射線を巡る議論を振り返った。
2007年勧告、採用
ICRPは、放射線による被ばくを管理、制御することで人の健康を守るための基準をつくり、提言する国際機関。原発事故後、政府が避難指示や除染などを行う際の基準として採用したのはICRPの「2007年勧告」だった。
原発事故のような異常事態を「緊急時被ばく状況」、身近な環境中に放射線を出す物質が管理を実施する前から存在する状況を「現存被ばく状況」と定義。放射線を計画的に管理することができる、いわば平常の状態は「計画被ばく状況」としており、それぞれ20~100ミリシーベルト、1~20ミリシーベルト、1ミリシーベルト以下と、被ばく線量の管理目標の範囲がある。
甲斐は「その時々の状況に応じて可能な放射線防護対策はある。それぞれの数値は、被ばく線量を抑える目安として幅を持たせ、各国はこの範囲の中で具体的な管理目標を定めるという仕組み。しかも、なるべく元に近い状態を目指すのが本来の趣旨」と説明する。しかし、原発事故まで放射線と向き合ってこなかった国内の受け止めは違った。
緊急時の対話の在り方
(略)
100ミリシーベルトは、被ばくによる臓器などへの影響が現れず、集団での影響を観察できなくなる下限の数値、20ミリシーベルトは放射線業務に従事する人に定められた年間被ばく線量、1ミリシーベルトは一般人を対象に平常時に管理する被ばく線量。あくまで目安であり、健康影響や危険性の境界を示す数値ではなかった。
だが、社会は状況に白黒を付ける基準を求めた。不安を解消しようと「100ミリシーベルト以下は大丈夫」と説明した専門家もいた。すると被災地の本県などから「平常時は1ミリシーベルトだろう」「20ミリシーベルトでも高い」という議論が起こった。甲斐は当時の状況を「非常時には、安全だというよりも、危ないから気を付けろという話が届きやすい。理解してもらうのは難しかった」と語る。