汚染状況はまだすべて明らかになっていないのに、、なぜ軽々しく「帰還」を言うのか。
土方学者一昨年の震災からの二年間、私は福島県内の各地をホームステイしながら、現地での調査を続けてきました。
ニッカボッカ姿で住民の方々と一緒に土を掘り返し、除染作業を行ってきたからでしょう、いまでは「土方学者」と親しみを込めて呼ばれています。これを私は最大の褒め言葉だと思っているんです。
福島第一原子力発電所での事故以降、これまでに九〇〇〇人以上の内部被ばく調査を行なう傍ら、二本松市やいわき市の志田名地区における「放射能汚染地 図」の作成など、月のうち三分の二は福島県内で調査を行っています。残りの三分の一はライフワークであるチェルノブイリの調査でウクライナに滞在している ため、休みというものが全くない文字通り年中無休の日々を送ってきました。(略)
地域の分断
さて、この二年間の日々を振り返る際、私の胸に繰り返し浮かぶ言葉があります。それは「分断」という言葉です。
原発事故によって、福島は幾重にもわたって引き裂かれました。原発の二〇キロ圏内、三〇キロ圏内と圏外、避難地区からの避難者と彼らを受け入れた地域の住民、さらにはそこから県外へ避難した人たち……。家族が離れ離れになった方々が大勢います。
しかし国の施策はただでさえ分断されてしまっている人々を、さらなる分断に追いやる「分断政策」になっているのではないか、と私は危惧しています。
象徴的なのが原発立地市町村の一つである双葉町の状況でしょう。
昨年一二月、双葉町では井戸川克隆町長と町議会の対立から、町長の不信任案が可決されました。今年一月に井戸川町長は辞職。ICPRが定める年間一 mSvを達成できない限り帰還は認められないとする井戸川町長に対し、中間貯蔵施設の受け入れや除染について原発立地八カ町村で足並みをそろえるべきだ、 という議会の主張がぶつかり合った結果でした。
そんななか、双葉町の「復興まちづくり委員会」の有識者委員である私は、同町への帰還可能時期の推定を依頼され、町の汚染状況を調査することになりまし た。そこでゲルマニウム半導体検出器という高性能な装置で計測すると、双葉町内には未だ酷い汚染地域が多くあることが分かってきたのです。
特にセシウムやプルトニウムを濃縮する地衣類は汚染度が高く、キログラムあたり、どれも五〇万ベクレル、高いもので三六〇万ベクレルという凄まじい数値が出ました。
地衣類の繁殖する場所は、小さな子供が好んで遊ぶ路地裏や日陰に多くあります。そのことを考慮すれば非常に危険であり、場所によっては毎時二〇μSvを 超える地域もある。同じ地域の墓地では六〇μSvを超える場所も存在しています。それが事故から一年七カ月経った時点での町の現実なのです。
双葉町の最も汚染度の高い地域を基準とすると、土壌に放射性物質が沈んでいくことによる自然減衰を考慮しない場合、一時間当たりの空間線量が〇・一μSvになる時期は約一六五年から一六九年後という試算になります。
このような高線量の地域を除染したところで、果たしてその推定年数を変えることができるのか。さらにセシウムだけではなく、ストロンチウムやプルトニウ ムは原発直近の町で濃度が高い可能性もあります。それらの危険性をきちんと証明する前に、「帰還可能」という決定を軽々しく言うべきではない、というのが 私の現地を調査しての結論でした。
一方で双葉町には福島市内や郡山市内よりも線量の低い地域があるのも事実です。では、汚染レベルが地域によって異なる中で、それを「いますぐに帰れる地域」「数年後に帰れる地域」「当分帰れない地域」に分けてもよいものなのでしょうか。
決断するのは最終的に双葉町の方々だとはいえ、こうした帰還のやり方は町の「分断」をより深めるに過ぎないと私は考えています。同じ地域の中に帰れる人 がいる一方で、帰ることのできない人がいる。そこに賠償金の金額の差が生まれ、住民同士のいがみ合いがさらに生じてしまうのだとすれば――。果たしてそれ は双葉町の人々の望むことなのでしょうか。私にはそうは思えません。
一部の有識者の中には「それでも帰りたい人たちを無理に引き止める必要はない」という意見もあります。しかし、実際に帰還を強く望んでいるのがお年寄であることの意味を、まず私たちは考えなければなりません。(略)
放射能を調べるという作業は、世の中の見えなかった問題、隠されていた問題を焙り出す作業と切っても切れない関係にあります。だからこそ、研究者という立 場だけで物事を見ていると、必ず見落としが生じてしまう。だからまずは一人の市民としての視点を持ったうえで、どこから切りこんで行くかを研究者の目線で 考える必要がある。そして「分断政策」によって国の支援の規模が縮小されていく恐れがあるならば、そこから浮かび上がる様々な現実をしっかりと見なければ ならないし、伝えなければならない。
その意味で私にとって福島での活動は「研究」ではありません。あくまでも「調査」として人々の生活の中に分け入っていく。そこに暮らしている人、暮らさ ざるを得ない人、さらには県外に避難された方々も含めて、「研究」という視点で扱ってはならないのがこの原発事故の問題の本質なのです。(略)
市民科学者を育てる
そこで私は特定非営利活動法人「放射線衛生学研究所」を母体に、「市民科学者養成講座」と名付けた講座を各地で行っています。「市民科学者」とは高木仁 三郎先生の著書『市民科学者として生きる』から付けたもので、原発事故以後の日本で生活する上での重要なキーワードだと思っています。
私がこの言葉にこだわるのは、専門家の視点だけでは放射能汚染の実態が正確にはつかめないからです。専門家は土壌を取って調べることはできます。しか し、その地域で子供たちがどのように遊び、どんな場所に行きたがるのかは知りません。また、汚染地図における線量の違いの理由も、実際にそこで生活してい る人でなければ分からないことが多いのです。(略)
よって私は「市民科学者養成講座」を開催するとき、「みなさんは市民科学者です。市民科学者として知り得る情報には、僕が知らないものがたくさんありま す。それを教えてください」と必ず語りかけています。分からないことを彼らに教わりながら、ともに考え、一つひとつの問題に向き合い、自分たちなりの答え を一緒に出していくのです。
私の専門家としての使命は、福島に暮らす人々の中で粘り強く調査を続けることであるとともに、こうした「市民科学者」を一人でも多く育てていくことです。
福島の再生の形はまだまだ見えません。だからこそ、専門家としての自分がそのようにできることを、たとえ小さくとも粛々とやっていかなければならない。 今後も私自身の生活の一部としてこの問題を考え抜き、決してくじけてはならないと自分に言い聞かせながら、活動を続けていきたいと思っています。
Featured Topics / 特集
-
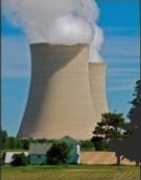
A nuclear power plant in Byron, Illinois. Taken by photographer Joseph Pobereskin (http://pobereskin.com). カレンダー
-
Latest Posts / 最新記事
- Holtec’s announcement that Palisades has transitioned back to “operations status” via Beyond Nuclear 2025/08/27
- Israel attacks Iran: What we know so far via Aljazeera 2025/06/13
- 核ごみ施設受け入れゼロ 全国47知事アンケートvia YAHOO!JAPANニュース (共同) 2025/06/12
- Trump Administration Gutting Regulatory Agency, Recent Nuclear Incidents, Coverup: No Time to Open Illinois for More Nuclear Power, Nuclear Watchdog Group Asserts via Nuclear Energy Information Service Illinois 2025/05/28
- Fukushima soil headed to Japan PM’s flower beds to allay nuclear safety fears via The Guardian 2025/05/28
Discussion / 最新の議論
- Leonsz on Combating corrosion in the world’s aging nuclear reactors via c&en
- Mark Ultra on Special Report: Help wanted in Fukushima: Low pay, high risks and gangsters via Reuters
- Grom Montenegro on Duke Energy’s shell game via Beyond Nuclear International
- Jim Rice on Trinity: “The most significant hazard of the entire Manhattan Project” via Bulletin of Atomic Scientists
- Barbarra BBonney on COVID-19 spreading among workers on Fukushima plant, related projects via The Mainichi
Archives / 月別アーカイブ
- August 2025 (1)
- June 2025 (2)
- May 2025 (10)
- February 2025 (1)
- November 2024 (3)
- October 2024 (1)
- September 2024 (5)
- July 2024 (4)
- June 2024 (3)
- March 2024 (1)
- February 2024 (6)
- January 2024 (4)
- November 2023 (8)
- October 2023 (1)
- September 2023 (7)
- August 2023 (5)
- July 2023 (10)
- June 2023 (12)
- May 2023 (15)
- April 2023 (17)
- March 2023 (20)
- February 2023 (19)
- January 2023 (31)
- December 2022 (11)
- November 2022 (12)
- October 2022 (7)
- September 2022 (6)
- August 2022 (22)
- July 2022 (29)
- June 2022 (15)
- May 2022 (46)
- April 2022 (36)
- March 2022 (47)
- February 2022 (24)
- January 2022 (57)
- December 2021 (27)
- November 2021 (32)
- October 2021 (48)
- September 2021 (56)
- August 2021 (53)
- July 2021 (60)
- June 2021 (55)
- May 2021 (48)
- April 2021 (64)
- March 2021 (93)
- February 2021 (69)
- January 2021 (91)
- December 2020 (104)
- November 2020 (126)
- October 2020 (122)
- September 2020 (66)
- August 2020 (63)
- July 2020 (56)
- June 2020 (70)
- May 2020 (54)
- April 2020 (85)
- March 2020 (88)
- February 2020 (97)
- January 2020 (130)
- December 2019 (75)
- November 2019 (106)
- October 2019 (138)
- September 2019 (102)
- August 2019 (99)
- July 2019 (76)
- June 2019 (52)
- May 2019 (92)
- April 2019 (121)
- March 2019 (174)
- February 2019 (146)
- January 2019 (149)
- December 2018 (38)
- November 2018 (51)
- October 2018 (89)
- September 2018 (118)
- August 2018 (194)
- July 2018 (22)
- June 2018 (96)
- May 2018 (240)
- April 2018 (185)
- March 2018 (106)
- February 2018 (165)
- January 2018 (241)
- December 2017 (113)
- November 2017 (198)
- October 2017 (198)
- September 2017 (226)
- August 2017 (219)
- July 2017 (258)
- June 2017 (240)
- May 2017 (195)
- April 2017 (176)
- March 2017 (115)
- February 2017 (195)
- January 2017 (180)
- December 2016 (116)
- November 2016 (115)
- October 2016 (177)
- September 2016 (178)
- August 2016 (158)
- July 2016 (201)
- June 2016 (73)
- May 2016 (195)
- April 2016 (183)
- March 2016 (201)
- February 2016 (154)
- January 2016 (161)
- December 2015 (141)
- November 2015 (153)
- October 2015 (212)
- September 2015 (163)
- August 2015 (189)
- July 2015 (178)
- June 2015 (150)
- May 2015 (175)
- April 2015 (155)
- March 2015 (153)
- February 2015 (132)
- January 2015 (158)
- December 2014 (109)
- November 2014 (192)
- October 2014 (206)
- September 2014 (206)
- August 2014 (208)
- July 2014 (178)
- June 2014 (155)
- May 2014 (209)
- April 2014 (242)
- March 2014 (190)
- February 2014 (170)
- January 2014 (227)
- December 2013 (137)
- November 2013 (164)
- October 2013 (200)
- September 2013 (255)
- August 2013 (198)
- July 2013 (208)
- June 2013 (231)
- May 2013 (174)
- April 2013 (156)
- March 2013 (199)
- February 2013 (191)
- January 2013 (173)
- December 2012 (92)
- November 2012 (198)
- October 2012 (229)
- September 2012 (207)
- August 2012 (255)
- July 2012 (347)
- June 2012 (230)
- May 2012 (168)
- April 2012 (116)
- March 2012 (150)
- February 2012 (198)
- January 2012 (292)
- December 2011 (251)
- November 2011 (252)
- October 2011 (364)
- September 2011 (288)
- August 2011 (513)
- July 2011 (592)
- June 2011 (253)
- May 2011 (251)
- April 2011 (571)
- March 2011 (494)
- February 2011 (1)
- December 2010 (1)
Top Topics / TOPトピック
- anti-nuclear
- Atomic Age
- Capitalism
- East Japan Earthquake + Fukushima
- energy policy
- EU
- France
- Hanford
- health
- Hiroshima/Nagasaki
- Inequality
- labor
- Nuclear power
- nuclear waste
- Nuclear Weapons
- Radiation exposure
- Russia/Ukraine/Chernobyl
- Safety
- TEPCO
- U.S.
- UK
- エネルギー政策
- メディア
- ロシア/ウクライナ/チェルノブイリ
- 健康
- 公正・共生
- 兵器
- 再稼働
- 労働における公正・平等
- 原子力規制委員会
- 原発推進
- 反原発運動
- 大飯原発
- 安全
- 広島・長崎
- 廃炉
- 東京電力
- 東日本大震災・福島原発
- 汚染水
- 米国
- 脱原発
- 被ばく
- 資本主義
- 除染
- 食の安全
Choose Language / 言語



