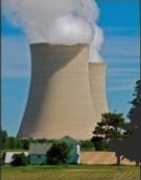ディレクターの私のふるさとは、福島県浪江町。10年前の原発事故で全町避難となった町だ。原発事故直後から福島に通い、廃炉や復興の現状について番組を作ってきた私。常に感じてきたのは、ふるさとの人たちの複雑な思いを、より深く伝えたいという思いだった。実家の家族が被災した、いわば“半当事者”だから伝えられる、大事な話があるような気がしたのだ。
しかし、思いがけず、“当事者”だからこそ聞けないことがある、という壁に突き当たった。その時、大きな助けになったのは、一緒に取材を行った“当事者ではない”カメラマンの存在。2人で苦悩しながら「なにを聞き、伝えるべきなのか」を模索しつづける日々だった。
(名古屋放送局ディレクター 水谷宣道、映像センターカメラマン 井上秀夫)
話を聞こうとしたのは、原発作業員や役場の職員など、事故後もしょっちゅう顔を合わせ、一緒に酒を飲んでいた同級生たち。しかし、『カメラの前で本音を話せば、誰に何を言われるかわからない』と、ことごとく取材を断られた。
長年メールのやり取りを続けていた親友とは連絡が取れなくなり、友人の女性からは『原発事故避難者だと知られ、子どもがひぼう中傷を受けたら、責任は取れるのか?』と、泣きながら訴えかけられた。『結局お前はよそ者。俺らの気持ちはわからない』とも言われた。
放射能汚染、賠償、避難者へのいじめなど、様々な問題が複雑に絡み合う原発事故の被災地。取材が簡単ではないことは知っているつもりだった。それでも、ふるさとの力にもなれるのではと始めた取材で拒絶され、長年続いてきた友人関係が、一瞬で崩れてしまいそうになるのは、つらいことだった。
なんとか友人の協力を得て、同世代たちの現状を描く35分のドキュメンタリー番組を完成させた。しかし、当初伝えたいと思っていたざらざらした本音や、原発事故の複雑さが、十分伝えきれたとは思えなかった。
[…]
原発事故前、2万1000人が暮らしていた浪江町。2017年に、町の中心部で避難指示が解除されたが、いま町で暮らしている人は、1600人余り(2021年3月現在)。仕事や子育てなど様々な事情から、2万人近くの当時の町民が、県内外で避難生活を送っている。
「浪江とのつながりを持ち続けたい」と、住民票を町に残したまま避難を続ける人も多かったが、今は、住民票を避難先に移す人も増えている。
事故から10年がたとうとしていたが、ふるさとの復興が進んでいるとはなかなか思えなかった。
取材への協力を頼むと、今度は、多くの人が「協力する」と言ってくれた。ある友人は「10年がたつ今なら話せる」と言い、別の友人は「話すことで自分なりにけりをつけたい」と言った。
思わぬ告白 町民を翻弄した「賠償」
先入観を持たずに、ふるさとの人々の声に耳を傾けてみようと始まった取材。テーマが少しずつ見えてきたのが、友人の父親を取材したときだった。
事故後、町の幹部として復興に取り組んできた男性は、町長選に立候補するものの落選。その後、首都圏に住宅を購入し移住した。
取材中、雑談をしていると、突然男性が語りだした。「俺をだめにしたのは賠償だ」何を言い出すのかと少し驚き聞き返すと、男性はこう続けた。
「町の人たちに『賠償をもらったからあいつは町を出た』と陰口を言われていたが、あながち間違いじゃないんだよ。たしかに、復興のために頑張っていたときは、賠償なんてどうでもよかった。でも、何かに挑戦してだめだったとき、賠償が効いてくるんだ。俺は町長選に落ちたとき、これだけの金があれば、もう無理しなくていいかなと思った」
ためらう自分 賠償について聞く事
原発事故の被害の償いである「賠償」。土地、家屋、精神的苦痛など、さまざまな損害についての賠償が、東京電力から被災者に支払われた。
着の身着のままの避難を余儀なくされた住民たちの生活再建などに大きな役割を果たした一方で、賠償をめぐり、被災者が、「賠償金をもらい、仕事をせずに不自由の無い暮らしをしている」など、いわれなき中傷や差別を受けることもあった。
デリケートな問題で、誤解や差別につながりやすいこともあり、住民はこれまで多くを語ってこなかったが、住民のさまざまな判断に大きく影響を与えた要素であることは間違いなかった。
男性の取材を機に、私は、ふるさとの人たちに「カネ」についてきちんと聞くことで、復興とは何だったのかを考えていきたいと思うようになった。
しかし、私は、再び大きな壁にぶつかった。聞くべきと思った質問を、なかなか聞けなくなっていったのだ。踏み込んだ質問をしようとすればするほど、その刃が自分自身に向かってくるような気持ちがしたのだ。
ある夫婦に話を聞いたときのことだった。彼らが暮らしていた地区は、当初、数年後の帰還をめざす「居住制限区域」となる案を町から提示されたが、地区の区長らが変更を要望し、長期間帰ることが難しい「帰還困難区域」となった。
当時、帰還困難区域の住民のほうが、受け取れる賠償の額が多いことになっていたため、他の地域の人からは、“カネ目当て”の選択ではないかと陰口をたたかれたこともあったという。
私は夫婦に、賠償を多く得て「帰還困難区域」となることをどう思ったのか、陰で言われていたことが事実だったのか、確かめたいと思った。だが、結局聞けなかった。
私は、賠償金をもらっていた私の両親から、賠償をもらいたくてもらっているわけでもないことや、後ろめたさすら感じていること、そして、周りの目を気にして、肩身の狭い思いで暮らしていることなどを聞かされていた。それがわかっていて、答えづらいであろう問いを突きつけることはできなかった。
結局、井上カメラマンが、質問をする趣旨を説明したうえで、その問いを発した。すると夫は、しばらく考えた末、「戻れない以上、高いお金がもらえるなら、それはそれでいいなとは思った」と答えた。
同時に、戻れるなら賠償はいらないと思っていたし、愛着ある家や持ち物に値段をつけられることも嫌だったと語った。
おそらく、ふるさとに戻ることが現実的に難しいという状況に直面して、賠償金をもらうという苦渋の選択をせざるを得なかったのだろう。ふるさとの人たちが抱えてきた葛藤の一端をまたかいま見た気がした。
廃炉・除染… 原発のそばで生きるリアル
除染作業に関わる同世代の友人へのインタビューも、精神的にこたえるものだった。町では、廃炉や除染など、原発事故の後処理に、今も多くの住民が携わっていた。
被害を受けた当人たちが今も後処理に関わっている事実を、本人たちはどう捉えているのか?それは、「地域と原発」というテーマを考えるにあたり重要な問いだと、取材クルーでは考えていた。
しかし、私には聞くことができなかった。その質問には、「原発とともに暮らしてきた人たちは、結局これからも、原発に頼るしかないのではないか」という、よそ者目線の「哀れみ」が含まれる質問だと感じたからだ。
私自身これまで似たような質問をされ嫌な思いをしてきたし、この10年、同じ経験をした町の人たちも多いのではないかと思っていた。
結局、質問できない私を見かねて、井上カメラマンが聞いた。すると、その場にいた別の町民が「また、そのステレオタイプな質問ですか」と嫌みを言った。外からの遠慮のない視線にさらされ続けてきた彼らのせめてもの抵抗だったのだろう。
それでも、友人はしばらく考え込み、ことばを絞り出し、真摯(しんし)に答えた。「事故前はそれで町が潤っていたし、しょうがないよね。今はその仕事しかないし、町のこれからの経済をまわしていくためには、廃炉はやはり大事だよね」
その答えには、廃炉が続く原発のそばで生きる友人のリアルな感情が詰まっているように思えた。
[…]