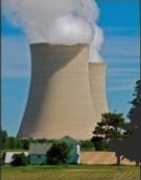三浦英之(新聞記者、ルポライター)
武藤類子(福島原発告訴団団長)
東京電力福島第一原発の事故発生から10年。原発事故にまつわる問題は多様化・複雑化する一方であるのに対し、メディアがそれを扱う機会は徐々に減りゆき、人々は原発事故を「過去のもの」だと捉え始めてはいないか。そんな潮流に抗うためにも、10年が経過した今だからこそ、福島の現実を知る人たちと議論を重ねていきたい。
私はこの春までの約3年半、新聞記者として福島に勤務した。過酷な現実の中を必死に生き抜こうとする人々を取材する一方で、この未曽有の原子力災害を今後、どのようなかたちで未来に語り継いでいくのか、ということが大きな関心事の一つであった。つまり、福島における「石牟礼道子」は誰なのか、という問いである。3年半に出会った関係者に聞くと、彼らの多くが「それは類子さんだと思う」と口をそろえた。「武藤さん」ではなく、彼女は被災地で暮らす人々に「類子さん」、あるいは「東北の静かなる鬼」と呼ばれていた。(三浦英之)
(略)
武藤 2011年に原発事故が起きたときに抱いたのは、「悲しみの中にある怒り」でした。それを表現したのがあの言葉だったのです。東北の民はかつて、中央政府から「鬼」にたとえられました。荒々しくて、きちんと統治されていない、恐ろしいものとしてずっと扱われてきたのです。ところが、東北に伝えられている民族舞踏の中で表現される鬼というのは、また違った一面があります。例えば岩手の鬼剣舞(おにけんばい)は、鬼のような恐ろしい形相の面をつけた迫力のある踊りですが、実は不動明王などの仏の化身を表現したものなのです。「鬼」というのは、東北の人たちが中央政権にどのように扱われてきたかという、悲しい一面を象徴していると思うのです。
(略)
武藤 蝦夷の時代の抵抗や、戊辰戦争、明治の自由民権運動など、東北の人々は中央政権に対して常に従順だったわけではなく、激しく抗ってきたという歴史もあります。東北の人の血の中には、そうした静かに燃える怒りが、今でもあるんじゃないかと思っています。
原発裁判に見る東京電力の二面性
三浦 武藤さんは、福島原発告訴団の団長として、東京電力の幹部らに対して2012年に刑事告訴をして闘ってこられました。現在は控訴中ですが、2019年の東京地裁での無罪判決は、どのように受け止めましたか。
武藤 私は38回の公判をすべて傍聴しました。法廷では、今まで隠されていたメールや議事録が証拠として次々に出てきました。例えば、東電社内では文科省の地震調査研究推進本部が2002年に発表した「地震発生可能性の長期評価」を取り入れる前提でシミュレーションをして、15.7メートルの津波が襲来する可能性があることがわかりました。そこでは、津波が来た場合に何メートルの防潮堤が必要になるかを示す図面も作られていた。3人の被告人たち(東電の勝俣元会長、武藤元副社長、武黒元副社長)は大津波が来る可能性があるという報告を受けていたのに、結局、対策は取られなかったのです。
(略)
武藤 でも、個人として訴えるしか、手段がないのです。無罪判決が言い渡されたときには、「ああ、この国は誰も責任を取らない。司法までもがそうなのか」という、非常に深い絶望を感じました。被害者の誰がこんなことで納得できるでしょうか。
三浦 僕も、誰も納得はできないだろうな、と思いました。東電は、テレビや被災者の前では土下座までして「申し訳ありませんでした」と謝るのに、最終的に責任を迫られるADR(裁判外紛争解決手続)や裁判などでは絶対に譲らない。言っていることとやっていることがまるで違う。被災した多くの方々は、東電のそうした二面性を知り抜いているわけですから……。
武藤 私は、「脱原発福島ネットワーク」(1988年創設)という市民団体で、プルサーマル計画の中止や相次ぐ事故・トラブルの原因追及などについて、東京電力との交渉を30年近く続けてきました。事故後の2年半ぐらいは、中断していましたが、今も2カ月に1回くらい2時間、東電の広報担当者と市民とで交渉をしています。彼らは、毎回「申し訳ありませんでした。ご迷惑とご心配をお掛けしています」と言うのですが、事故後の対応や言動を見てもほんとに彼らが反省しているなという感覚は、とても持てないんですよね。その繰り返しで胃が痛くなるし、本当にイヤになるんです。
(略)
武藤 原告の福島の人々が何を失ったのかということが、まったく理解されていないのだと思います。失われたものの深さは、金額に換算することはできません。いろんな裁判の中で、「ふるさと喪失」は失われたものとして認めらないことが多いです。
福島とオリンピック
三浦 武藤さんは、2020年の福島での集会のスピーチで、オリンピックについてこのように話していました。
「莫大なお金がこのオリンピック、聖火リレーにつぎ込まれています。さまざまな問題がオリンピックの陰に隠され、遠のいていきます。オリンピックが終わった後に、何が残るのかとても不安です。私たちは、うわべだけの『復興した福島』を知ってほしいのではなく、たった9年では解決できない問題が山積した、とても苦しい、とても大変な原発事故の被害の実情こそを、世界の皆さまに知ってもらいたいです」(武藤類子『10年後の福島からあなたへ』大月書店、2021年)
(略)
武藤 最初は、復興五輪と言っていたのに、復興なんかどっかにいってしまった。そのあとのコロナ克服にしても、何も解決していません。最初から全部嘘なんだなと思いますね。
(略)
武藤 福島の原発も東京オリンピックも、最も大切にされるべき命や健康というものが、まったく顧みられていないというのが、一番大きな共通点だと思います。原発もオリンピックも、巨大な力で実現していくために、誰かを犠牲にすることをまったく厭わない。特に私が怒っているのは、子どもを動員するということです。事故後に原発作業員たちの中継基地となったJヴィレッジが、聖火リレーの出発地点に決まり、地元の子どもたちが芝を植え替えるために動員されました。フレコンバッグ置き場だった福島市の運動公園も、野球とソフトボールの会場に決まり、小学生たちが花植えの作業に動員されられたりしました。福島では安全を宣伝するための一番の広告塔に、ずっと子どもが使われてきたんです。オリンピックでも、このコロナ禍の中であっても「学校連携チケット」で子どもを動員しようとしていたことが驚きでした。
(略)
武藤 今、福島第一原発の周辺には、「福島イノベーション・コースト構想」の一環で国際教育研究拠点の設置が計画されています。これは、アメリカ、ワシントン州の「ハンフォード核施設」(ワシントン州)の周辺地域をモデルにすると言っているんです。ハンフォードは、マンハッタン計画において長崎に落とされた原爆の材料であるプルトニウムを製造した施設ですが、その周辺は、深刻な放射性物質の漏洩や実験的な拡散によってアメリカで最も汚染された地域です。廃炉や除染技術の研究所や関連する企業によって発展をしましたが、周辺住民を犠牲にすることを厭わずにやってきた歴史があります。
三浦 ハンフォードに倣って、産学官民の調整役となる「福島浜通りトライデック」という民間組織もできました。今までのように官製ではなくて、市民団体に見えるようになっている……。原子力ムラが市民団体のような顔をして国の原発政策を後押しするという、今までにはなかった新しいやり方にならないか、懸念しています。
武藤 イノベーション・コースト構想は「浜通りの輝かしい未来をつくりましょう」と夢を見せながら、実際には原子力産業が支配をし、やがてまた住民が犠牲にされていくのではないかという不安が、私にはどうしてもあります。原発事故直後から、福島県には「夢」とか「希望」とか「安全」とか「絆」という言葉が氾濫して、みんなで前を向いて進んでいかなければいけないという風潮がありました。私たちは絶望すらさせてもらえなかったのです。
(略)
武藤 本当は、人々の中に不安がないわけではないのです。でも、何かに背中を押されるように、口をつぐみ「あきらめの境地」へ連れていかれたんじゃないかな。食品汚染や健康被害、あるいは汚染土や汚染水にしても、一見それぞれ別の問題であるように見えますが、実はそうではありません。それらはすべて、「放射能というものは怖くないんだ」という一つの考え方に行き着くのです。放射能が怖くないと思わせることで、現実を見させないようにしている。原発事故から10年たった今から見ると、それらは放射線防護の基準や考え方を大幅に緩め、原子力産業の復活を狙って仕組まれたのではないか、と感じています。まやかしの「夢」や「希望」に惑わされないためには、一度この絶望を、目を凝らして見つめなければいけないと思うのです。生きていく中で大きな出来事に出会ったときには、その事実に絶望して打ちのめされるという過程が必要なんです。絶望をしっかりと見つめるという過程を経てはじめて、私たちは少しずつ立ち直っていくことができるのだと思います。