日本の原子力産業で、初めて被ばくによる死者が出たのが、1999年に起こったJCO臨界事故だった。この20年の間に、福島第1原発事故も発生。二つの原子力災害から浮かび上がる課題を追った。
「バシッ」。99年9月30日、核燃料を加工していた「ジェー・シー・オー(JCO)」東海事業所(茨城県東海村)で異音とともに青い閃光(せんこう)が放たれた。その瞬間、放射性物質のウラン溶液を扱う作業中だった社員の大内久さんと篠原理人(まさと)さんの体を、強烈な放射線が通過した。
核分裂が連鎖的に続く「臨界」状態が生じ、放射線を遮るものがない「裸の原子炉」ができあがっていた。被ばくした大内さんらを治療したのが、東京大病院で救急部・集中治療部長を務めていた前川和彦さん(78)だった。「やけどの専門家である私でさえ、毎日驚くような患者の変化だった。治療は海図のない航路だった」
× ×
急性の大量被ばくで、大内さんらの体は新たな細胞を作れなくなった。日焼けしたような肌は徐々に皮がむけて水ぶくれのようになっていた。搬送された当初、大内さんは前川さんが「本当に大量に被ばくしたのか」と思うくらい落ち着き、意識もはっきりしていた。しかし、入院4日目には検査の多さに「おれはモルモットじゃない」と訴えた。
数日後には薬の影響もあって徐々に意識が遠のいた。医療スタッフによる大内さんの83日間の治療記録には、刻々と変化していく体の状態が記されている。A4判用紙に印刷すると400ページ超。大内さんは99年12月に当時35歳で、篠原さんは翌年4月に同40歳で亡くなった。
× ×臨界事故前までは国内で原子力事故は起きないとされ、「被ばく医療」という言葉は安全神話の中でタブーだった。95年の阪神大震災をきっかけに、原子力災害時の医療が議論された時も「被ばく」の表現を避け「緊急時医療」と呼ばれた。「『海図』以前に、船自体の整備が進んでいなかったようなもの」(前川さん)だった
(略)
臨界事故と知らされず、救急隊員も被ばくした。受け入れ先が決まったのは事故から約75分後。入院した社員3人の本格的な医療体制が組まれたのは、事故翌日からだった。
急性放射線障害の治療例は海外でも少なく、治療はいろいろな文献を見ながら手探りで進められたという。
× ×(略)
急性被ばくを念頭に、こうした医療機関のスタッフや立地自治体や消防、警察の職員らが、定期的に開かれていた公益財団法人「原子力安全研究協会」の講習などに参加。事故に備えたはずだった。
ところが、2011年3月11日の東京電力福島第1原発事故では、放射性物質が広範囲に拡散。これらの医療機関も避難指示区域に含まれてしまい、病院としての機能を果たせなくなった。避難区域外でも、除染設備がなく住民の診療を断った災害時対応の病院があった。
その反省から原子力規制委員会は福島事故後、急性被ばくだけでなく、原発周辺の住民の除染も考慮した新たな医療体制の整備を目指した。原子力災害医療の中心となる「原子力災害拠点病院」を全国の約50病院に、拠点病院を支援する「協力病院」を約300病院に、それぞれ担ってもらう体制になっている。
Featured Topics / 特集
-
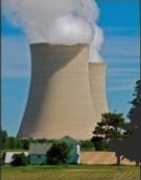
A nuclear power plant in Byron, Illinois. Taken by photographer Joseph Pobereskin (http://pobereskin.com). カレンダー
-
Latest Posts / 最新記事
- 被爆者らのゲノム解析 放影研方針、次世代への影響調査 via 日本経済新聞 2024/03/04
- 「おなか張る」から、亡くなるまで4カ月…生身の人間を苦しめたトロトラスト 知識ゼロから始まった「日本初の薬害」の取材 via 信濃毎日新聞 2024/02/29
- 福島第1原発で汚染水トラブル連発、経済産業相が東京電力を指導 「覚悟が見えない」地元もバッサリvia東京新聞 2024/02/23
- It’s not just toxic chemicals. Radioactive waste was also dumped off Los Angeles coast via LA Times 2024/02/21
- 仏で保管のプルトニウム 九州電力と四国電力の原発で利用へ via NHK News Web 2024/02/17
Discussion / 最新の議論
- Leonsz on Combating corrosion in the world’s aging nuclear reactors via c&en
- Mark Ultra on Special Report: Help wanted in Fukushima: Low pay, high risks and gangsters via Reuters
- Grom Montenegro on Duke Energy’s shell game via Beyond Nuclear International
- Jim Rice on Trinity: “The most significant hazard of the entire Manhattan Project” via Bulletin of Atomic Scientists
- Barbarra BBonney on COVID-19 spreading among workers on Fukushima plant, related projects via The Mainichi
Archives / 月別アーカイブ
- March 2024 (1)
- February 2024 (6)
- January 2024 (4)
- November 2023 (8)
- October 2023 (1)
- September 2023 (7)
- August 2023 (5)
- July 2023 (10)
- June 2023 (12)
- May 2023 (15)
- April 2023 (17)
- March 2023 (20)
- February 2023 (19)
- January 2023 (31)
- December 2022 (11)
- November 2022 (12)
- October 2022 (7)
- September 2022 (6)
- August 2022 (22)
- July 2022 (29)
- June 2022 (15)
- May 2022 (46)
- April 2022 (36)
- March 2022 (47)
- February 2022 (24)
- January 2022 (57)
- December 2021 (27)
- November 2021 (32)
- October 2021 (48)
- September 2021 (56)
- August 2021 (53)
- July 2021 (60)
- June 2021 (55)
- May 2021 (48)
- April 2021 (64)
- March 2021 (93)
- February 2021 (69)
- January 2021 (91)
- December 2020 (104)
- November 2020 (126)
- October 2020 (122)
- September 2020 (66)
- August 2020 (63)
- July 2020 (56)
- June 2020 (70)
- May 2020 (54)
- April 2020 (85)
- March 2020 (88)
- February 2020 (97)
- January 2020 (130)
- December 2019 (75)
- November 2019 (106)
- October 2019 (138)
- September 2019 (102)
- August 2019 (99)
- July 2019 (76)
- June 2019 (52)
- May 2019 (92)
- April 2019 (121)
- March 2019 (174)
- February 2019 (146)
- January 2019 (149)
- December 2018 (38)
- November 2018 (51)
- October 2018 (89)
- September 2018 (118)
- August 2018 (194)
- July 2018 (22)
- June 2018 (96)
- May 2018 (240)
- April 2018 (185)
- March 2018 (106)
- February 2018 (165)
- January 2018 (241)
- December 2017 (113)
- November 2017 (198)
- October 2017 (198)
- September 2017 (226)
- August 2017 (219)
- July 2017 (258)
- June 2017 (240)
- May 2017 (195)
- April 2017 (176)
- March 2017 (115)
- February 2017 (195)
- January 2017 (180)
- December 2016 (116)
- November 2016 (115)
- October 2016 (177)
- September 2016 (178)
- August 2016 (158)
- July 2016 (201)
- June 2016 (73)
- May 2016 (195)
- April 2016 (183)
- March 2016 (201)
- February 2016 (154)
- January 2016 (161)
- December 2015 (141)
- November 2015 (153)
- October 2015 (212)
- September 2015 (163)
- August 2015 (189)
- July 2015 (178)
- June 2015 (150)
- May 2015 (175)
- April 2015 (155)
- March 2015 (153)
- February 2015 (132)
- January 2015 (158)
- December 2014 (109)
- November 2014 (192)
- October 2014 (206)
- September 2014 (206)
- August 2014 (208)
- July 2014 (178)
- June 2014 (155)
- May 2014 (209)
- April 2014 (242)
- March 2014 (190)
- February 2014 (170)
- January 2014 (227)
- December 2013 (137)
- November 2013 (164)
- October 2013 (200)
- September 2013 (255)
- August 2013 (198)
- July 2013 (208)
- June 2013 (231)
- May 2013 (174)
- April 2013 (156)
- March 2013 (199)
- February 2013 (191)
- January 2013 (173)
- December 2012 (92)
- November 2012 (198)
- October 2012 (229)
- September 2012 (207)
- August 2012 (255)
- July 2012 (347)
- June 2012 (230)
- May 2012 (168)
- April 2012 (116)
- March 2012 (150)
- February 2012 (198)
- January 2012 (292)
- December 2011 (251)
- November 2011 (252)
- October 2011 (364)
- September 2011 (288)
- August 2011 (513)
- July 2011 (592)
- June 2011 (253)
- May 2011 (251)
- April 2011 (571)
- March 2011 (494)
- February 2011 (1)
- December 2010 (1)
Top Topics / TOPトピック
- anti-nuclear
- Atomic Age
- Capitalism
- East Japan Earthquake + Fukushima
- energy policy
- EU
- France
- Hanford
- health
- Hiroshima/Nagasaki
- Inequality
- labor
- Nuclear power
- nuclear waste
- Nuclear Weapons
- Radiation exposure
- Russia/Ukraine/Chernobyl
- Safety
- TEPCO
- U.S.
- UK
- エネルギー政策
- メディア
- ロシア/ウクライナ/チェルノブイリ
- 健康
- 公正・共生
- 兵器
- 再稼働
- 労働における公正・平等
- 原子力規制委員会
- 原発推進
- 反原発運動
- 大飯原発
- 安全
- 広島・長崎
- 廃炉
- 東京電力
- 東日本大震災・福島原発
- 汚染水
- 米国
- 脱原発
- 被ばく
- 資本主義
- 除染
- 食の安全
Choose Language / 言語



