(抜粋)
重い口開いた裁判官
日本の裁判官は自分がかかわった裁判について語ることは極めてまれだが、二人の朝日新聞社記者が、原発訴訟にかかわった裁判官に粘り強く働きかけ、10数人の裁判官から話を聞き、原発訴訟の難しさ、特殊性を聞き出してまとめたのが本書『原発に挑んだ裁判官』(朝日新聞出版)である。
原子力発電所は、日本の原子力研究者、技術者が総力を挙げて作っている高度な科学技術の巨大システムである。いかに優秀な裁判官といえども、そうした代物の中に、国民の安全性を損なう欠陥を見つけ、正すことは至難の業である。最高裁では、こうした国策も絡む訴訟を、「複雑困難訴訟」とよんでいるのだという。
地方裁判所の裁判官の中には、敢然とこの難問に取り組んだ裁判官たちがいた。たとえば、2006年に北陸電力志賀原発2号機の運転差し止め訴訟では、「電力会社が想定しているM6.5の直下型地震では、耐震性が十分ではない」として、井戸謙一裁判長は、運転差し止めを求めた住民側勝訴の判決を言い渡した。しかし、この裁判は、高裁で住民側逆転敗訴、2010年秋に最高裁でも住民敗訴となった。東日本大震災で福島原発が津波に襲われて事故を起こしたのはその4か月余り後の事だった。福島原発では、津波の前に地震そのものによって原発が壊れたという指摘も出されており、1審判決の先見性に驚かざるを得ない。
国策を忖度する最高裁事務総局
しかし、こうした数少ない判決は、高裁、最高裁でことごとく覆されている。その背景には、日本の裁判制度に巣くうゆがんだ官僚性があると本書は指摘している。
たとえば、本来は最高裁の事務事項を処理する庶務部のような組織だったはずの最高裁事務総局が、エリート裁判官の出世コースになっており、全国の裁判官の人事、予算、報酬などを牛耳っているのだという。
それどころか、そこからは、原発訴訟のような国策に絡む裁判では「行政庁のした判断に合理性、相当性があると言えるかどうかという観点から審査していけば足りるというべきであるように思われる……」などと、裁判官の判断を誘導するような見解を出している。この「見解」は、日本の原発訴訟に対する判断基準とみなされている伊方原発1号機に対する最高裁判決の論理を先取りした形になっている。
また、最高裁には判事を補佐する調査官という人たちがいる。彼らは高裁から上がってきた裁判について、過去の例に従って「上告棄却」「不受理」などの判断を下すのだが、最高裁判事が知らないうちに扱いが決まっていることもしばしばあるという。調査官は裁判官のエリートコースの一つで、最高裁事務総局などの経験者も多く、「過去の判例踏襲型の発想が強く、司法の硬直化の原因にもなっている」という研究者からの指摘もあるという。
日本では、三つの権力の中で司法権の弱さが目立つ。その元凶は、時の権力や国が進める国策を忖度しすぎる最高裁のエリートたちなのかもしれない。
Featured Topics / 特集
-
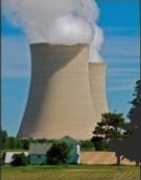
A nuclear power plant in Byron, Illinois. Taken by photographer Joseph Pobereskin (http://pobereskin.com). カレンダー
-
Latest Posts / 最新記事
- 被爆者らのゲノム解析 放影研方針、次世代への影響調査 via 日本経済新聞 2024/03/04
- 「おなか張る」から、亡くなるまで4カ月…生身の人間を苦しめたトロトラスト 知識ゼロから始まった「日本初の薬害」の取材 via 信濃毎日新聞 2024/02/29
- 福島第1原発で汚染水トラブル連発、経済産業相が東京電力を指導 「覚悟が見えない」地元もバッサリvia東京新聞 2024/02/23
- It’s not just toxic chemicals. Radioactive waste was also dumped off Los Angeles coast via LA Times 2024/02/21
- 仏で保管のプルトニウム 九州電力と四国電力の原発で利用へ via NHK News Web 2024/02/17
Discussion / 最新の議論
- Leonsz on Combating corrosion in the world’s aging nuclear reactors via c&en
- Mark Ultra on Special Report: Help wanted in Fukushima: Low pay, high risks and gangsters via Reuters
- Grom Montenegro on Duke Energy’s shell game via Beyond Nuclear International
- Jim Rice on Trinity: “The most significant hazard of the entire Manhattan Project” via Bulletin of Atomic Scientists
- Barbarra BBonney on COVID-19 spreading among workers on Fukushima plant, related projects via The Mainichi
Archives / 月別アーカイブ
- March 2024 (1)
- February 2024 (6)
- January 2024 (4)
- November 2023 (8)
- October 2023 (1)
- September 2023 (7)
- August 2023 (5)
- July 2023 (10)
- June 2023 (12)
- May 2023 (15)
- April 2023 (17)
- March 2023 (20)
- February 2023 (19)
- January 2023 (31)
- December 2022 (11)
- November 2022 (12)
- October 2022 (7)
- September 2022 (6)
- August 2022 (22)
- July 2022 (29)
- June 2022 (15)
- May 2022 (46)
- April 2022 (36)
- March 2022 (47)
- February 2022 (24)
- January 2022 (57)
- December 2021 (27)
- November 2021 (32)
- October 2021 (48)
- September 2021 (56)
- August 2021 (53)
- July 2021 (60)
- June 2021 (55)
- May 2021 (48)
- April 2021 (64)
- March 2021 (93)
- February 2021 (69)
- January 2021 (91)
- December 2020 (104)
- November 2020 (126)
- October 2020 (122)
- September 2020 (66)
- August 2020 (63)
- July 2020 (56)
- June 2020 (70)
- May 2020 (54)
- April 2020 (85)
- March 2020 (88)
- February 2020 (97)
- January 2020 (130)
- December 2019 (75)
- November 2019 (106)
- October 2019 (138)
- September 2019 (102)
- August 2019 (99)
- July 2019 (76)
- June 2019 (52)
- May 2019 (92)
- April 2019 (121)
- March 2019 (174)
- February 2019 (146)
- January 2019 (149)
- December 2018 (38)
- November 2018 (51)
- October 2018 (89)
- September 2018 (118)
- August 2018 (194)
- July 2018 (22)
- June 2018 (96)
- May 2018 (240)
- April 2018 (185)
- March 2018 (106)
- February 2018 (165)
- January 2018 (241)
- December 2017 (113)
- November 2017 (198)
- October 2017 (198)
- September 2017 (226)
- August 2017 (219)
- July 2017 (258)
- June 2017 (240)
- May 2017 (195)
- April 2017 (176)
- March 2017 (115)
- February 2017 (195)
- January 2017 (180)
- December 2016 (116)
- November 2016 (115)
- October 2016 (177)
- September 2016 (178)
- August 2016 (158)
- July 2016 (201)
- June 2016 (73)
- May 2016 (195)
- April 2016 (183)
- March 2016 (201)
- February 2016 (154)
- January 2016 (161)
- December 2015 (141)
- November 2015 (153)
- October 2015 (212)
- September 2015 (163)
- August 2015 (189)
- July 2015 (178)
- June 2015 (150)
- May 2015 (175)
- April 2015 (155)
- March 2015 (153)
- February 2015 (132)
- January 2015 (158)
- December 2014 (109)
- November 2014 (192)
- October 2014 (206)
- September 2014 (206)
- August 2014 (208)
- July 2014 (178)
- June 2014 (155)
- May 2014 (209)
- April 2014 (242)
- March 2014 (190)
- February 2014 (170)
- January 2014 (227)
- December 2013 (137)
- November 2013 (164)
- October 2013 (200)
- September 2013 (255)
- August 2013 (198)
- July 2013 (208)
- June 2013 (231)
- May 2013 (174)
- April 2013 (156)
- March 2013 (199)
- February 2013 (191)
- January 2013 (173)
- December 2012 (92)
- November 2012 (198)
- October 2012 (229)
- September 2012 (207)
- August 2012 (255)
- July 2012 (347)
- June 2012 (230)
- May 2012 (168)
- April 2012 (116)
- March 2012 (150)
- February 2012 (198)
- January 2012 (292)
- December 2011 (251)
- November 2011 (252)
- October 2011 (364)
- September 2011 (288)
- August 2011 (513)
- July 2011 (592)
- June 2011 (253)
- May 2011 (251)
- April 2011 (571)
- March 2011 (494)
- February 2011 (1)
- December 2010 (1)
Top Topics / TOPトピック
- anti-nuclear
- Atomic Age
- Capitalism
- East Japan Earthquake + Fukushima
- energy policy
- EU
- France
- Hanford
- health
- Hiroshima/Nagasaki
- Inequality
- labor
- Nuclear power
- nuclear waste
- Nuclear Weapons
- Radiation exposure
- Russia/Ukraine/Chernobyl
- Safety
- TEPCO
- U.S.
- UK
- エネルギー政策
- メディア
- ロシア/ウクライナ/チェルノブイリ
- 健康
- 公正・共生
- 兵器
- 再稼働
- 労働における公正・平等
- 原子力規制委員会
- 原発推進
- 反原発運動
- 大飯原発
- 安全
- 広島・長崎
- 廃炉
- 東京電力
- 東日本大震災・福島原発
- 汚染水
- 米国
- 脱原発
- 被ばく
- 資本主義
- 除染
- 食の安全
Choose Language / 言語



