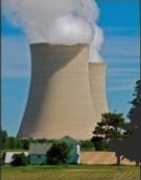報告者・翻訳者の花崎皋平さんの許可を得て掲載します
二〇一一年四月初め、ドイツを旅行していてフランクフルター・アルゲマイネツアイトゥング紙の四月三日日曜特集を手にする機会があった。日本の新聞には見られない非常に明確な主張の脱原発特集がなされていた。一面トップの見出しが「われわれの敵、アトム」で、「ビショップ・マルクス:早くやめよ。トリッティン:次期の任期中に脱却可能」という副題が付いていた。マルクスはミュンヘンのカトリック大司教、トリッティンは緑の党の代表である。
このうちビショップ・マルクスのインタビューに一面全部が割かれていた。それを読んで共鳴するところが多かったので、主な部分を紹介したい。インタビューは「われわれはもっと早く脱却しなければならないーー原発政治の倫理、限度の喪失、国家の委託に置ける教会の役割」と題されている。いかはその要約である。
人は高度に工業化された国土における原子エネルギーの危険について知っている。すでに以前から最終処理問題が解決されていないことを知っている。
原子力は過渡的技術であるというコンセンサスはすでにある。その過渡性をできるだけ引き延ばしたがっている若干の人たちがいる。昨年秋に、原発の運転期間を延長することにした政府の決定を、私は残念に思っていた。可能な限り、もっと早くわれわれは脱却すべきである。
この技術的、政治的、経済的問題に、ビショップはなにを寄与することができるかという質問に対して、彼はこう答えている。
「われわれはすべての世代に好ましくない結果をもたらす技術を信頼すべきかという倫理的問いに直面している。われわれはその問いにノウという。それは、われわれがすべてを市場にゆだねるべきではないという提言に関係している。エネルギーは他の商品と同じように取り扱うべきではない。われわれはその全部を政治的、社会的な枠組みに置かなければならない。その際、われわれはどのくらいの期間、影響と負担を我慢しなければならないかを考慮しなければならない。それは単に核エネルギーだけのことではない。われわれがどのような生活を望むか。その限度についての問題である。
ここで訳者の注釈を加えると、限度と訳したドイツ語はマースMassでヘーゲル論理学のカテゴリーでもあるが、淵原をたどればギリシャ哲学のカテゴリーでソープロシュネーである。この言葉は節制とも訳される。わきまえるべき限度を守る倫理的態度を意味する。成田空港建設反対の農民思想家が「腹八分目」の思想ということをいったが、具体的には欲望のままに振る舞うことを戒めるそうしたあり方である。原文に戻ろう。
われわれの生活スタイルは気候変動と資源節約に合致する福祉モデルに帰られなければならない。技術革新をもちいて効率を高め、より少ないエネルギーで必要を満たすようにすることである。ドイツがそれを示せば他の国を励ますことになるだろう。再生可能なエネルギーの建設をともなう(原発からの)脱却は可能である。われわれが自宅を持つ人びとのあまり生産性の高くないソーラー設備を公共料金で補助し、貧困な人に、より高くなる電気料金を補助する新しい分かち合いが人びとに支持されないとは思わない。ともかく新しい技術への道を開くことには意義があると思う。
エネルギーの値段が高くなるとしても、それを受け入れるか、という問いかけに対しては、エネルギーが実際に公正であればたぶん認める。しかし問題はよりひろい枠組みの中で議論されなければならない。その際、核エネルギーの場合、実際の価格が今日まで計算されていないこともきちんと考えるべきである。根本的な問題は、われわれがますます、もっとエネルギーの責任を負うことができるかどうかである。
成長にブレーキをかけるかどうかということについてはこう語っている。
成長の終わりという命題は誤っている。成長ということでなにを理解するかは新しく議論すべきである。いまはちょうど四旬節(断食の時)である。このときにマース(限度)のスピリチュアリティを擁護することはむずかしいことではない。
限度とか限界というが、それは具体的には何を意味するのかという問いに対しては、こう答えている。
それは最終的には創造者と被造物との区別である。被造物の限度を越えることはできないというところから、受容可能な人間像が導かれる。もしわれわれが原子力技術の計り知れない危険を、もっと後の世代の、責任のない人びとから取り除かないならば、限度を失っているというべきである。それは道路交通の危険とはまった別の事柄である。
この場合に、どこにその限界があるかをどうやって知るのか。
それは理性的な議論によって行うべきことである。それは骨の折れることであるが、できないことではない。
貴方の答えは聖書に書いてあることなのかという問いに対しての答えはこうである。
それは万人が持つことができる根本認識である。良否、正不正を判断できるためにキリスト者である必要はない。その判断は理性的で根元的で、すべての人間があとづけることができるはずである。
その判断に、核エネルギーに決別しなければならないという命題が属しているか、と問われて、グローバルにはまだそうではないとのべている。
このあと、現在のドイツの政府や議会と教会との関係についての質疑が続くがそれは事情がよくわからないので省略する。
これを読んで思ったことは、日本の新聞で原子力エネルギー利用に着いての倫理というようなことが話題にされたことはない、消費の抑制、人間の生活における根元的な節度とか、そのスピリチュアリティといったことが論じられることもない。要するに哲学も倫理もお呼びではないのである。
だから、エネルギーは他の商品と同様の商品とすべきではないという社会倫理的判断とか、正邪善悪の判断は万人に可能である。それは、理性が万人に備えられているからだ、というような哲学的な発想が生まれるわけもない。こういう意見の持ち主が大司教であり、原子力の倫理的問題についての連邦政府の委託に答える審議会のメンバーである。こうしたところに政治の質の違いを知らされる。
帰国後、四月一六日の朝日新聞夕刊に、メルケル首相が国内の原子力発電の運転期間を短くする法改正を行うとのべたことを報じ、彼女が記者会見で「われわれは皆、できる限り早く核エネルギーから脱却し、(風力などの)再生可能エネルギーへと乗り換えたいと考えている」と語ったと書いていた。
日本の政治も新聞も、今回の原発事故のはらむ社会倫理や哲学の問題を全く考えていない。一九四五年のアジア太平洋戦争敗戦の時と共通している。一億総懺悔して、みんなが被害者として悲しみあうだけなのだ。情けないことである。